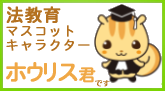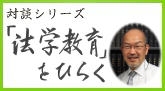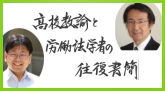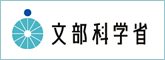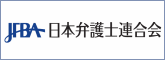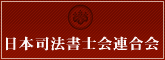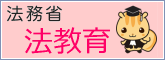法教育マスコットキャラクター人気投票、結果発表!
今回のマスコットキャラクターのデザイン公募には、426点ものご応募をいただき、特別審査員の審査を経て選出された10点のキャラクターの中から11月28日まで人気投票を行いました。
3471票もの投票をいただき、「最優秀賞」は、海山幸さんの「ホウリス君」に決定いたしました。

2014年12月に、最優秀賞・優秀賞の受賞者を表彰する法務大臣表彰式が開催されました。
表彰式の詳しい様子については、こちら(法務省ウェブサイト内ページ)をご覧ください。
法教育マスコットキャラクター人気投票を実施しています!
9月11日まで募集した法教育マスコットキャラクターのコンペティションには、なんと426点ものご応募をいただきました。
どれも力作揃いで、特別審査員の方々にはすべての作品をご覧いただき熱くご議論をいただいた結果、下記の10点のキャラクターが選出されました。
法教育のマスコットキャラクターにふさわしいと思うデザインに是非、皆さんの清き一票をお待ちしています。
特別審査員の先生方からの審査コメントをいただきました!
こちら(法務省ウェブサイト内ページ)をご覧ください。

投票期間は10月4日(土)~11月28日(金)(必着)です。
投票方法など詳細はこちら(法務省ウェブサイト内ページ)
法教育マスコットキャラクターの投票について
たくさんの方にご応募いただいた法教育マスコットキャラクターのデザイン・愛称案から、
ご覧の豪華な特別審査員の方々と法教育推進協議会によって、まずは数点が選出されます。
《特別審査員》(*敬称略)
| 藤 子 不二雄Ⓐ | (漫画家) | |
| 村 上 もとか | (漫画家) | |
| 一 条 ゆかり | (漫画家) | |
| 松 谷 孝 征 | (手塚プロダクション代表取締役社長) | |
| 鈴 木 晴 彦 | (集英社取締役) |
その後、選出された作品の中から、10月1日から11月末日(予定)でみなさんに、投票をしていただき、もっとも多くの票が集まったデザインが最優秀賞となります。
最優秀賞に投票してくださった方の中から抽選で50名に3000円の図書券をプレゼント!
投票にも奮ってご参加ください!(投票はお1人1回のみ可能です)。
投票方法の詳細は、この欄で追ってお知らせします。
法教育マスコットキャラクター大募集!
9月11日をもって募集を締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。
法は専門家だけのものではありません。「法教育」は、子供たちの未来を拓くためにも欠かせないもの。
法教育推進協議会と公益社団法人商事法務研究会は、「法教育」にもっと親しんでいただくために、「法教育」教材やイベントで活用するキャラクターを募集します。
デザインと愛称を募集するとともに、皆さんに投票で「法教育」マスコットキャラクターを選んでいただきます。
特別審査員は下記の方々です。(*敬称略)
| 藤 子 不二雄Ⓐ | (漫画家) | |
| 村 上 もとか | (漫画家) | |
| 一 条 ゆかり | (漫画家) | |
| 松 谷 孝 征 | (手塚プロダクション代表取締役社長) | |
| 鈴 木 晴 彦 | (集英社取締役) |
あなたの描いた作品が、これらの方々の目に留まるかも?!
たくさんのご応募お待ちしております!
応募方法など詳細はこちら(法務省ウェブサイト内ページ)をご覧ください。
平成25年度法教育懸賞論文受賞者の発表について
法教育推進協議会、日本司法支援センター(法テラス)、公益社団法人商事法務研究会の主催、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会の後援による平成25年度の法教育懸賞論文は、法教育推進協議会法教育普及検討部会において厳正な審査を行った後、法教育推進協議会での決議を経て次の受賞者が選定されました。
| 【日本司法支援センター賞】 | 河村 新吾氏(広島市立基町高等学校教諭〔当時〕) |
| 【公益社団法人商事法務研究会賞】 | 藤井健太郎氏(大垣市立上石津中学校教諭〔当時〕) |
| 【奨励賞】 | 藤井 剛氏(千葉県立千葉工業高等学校教諭) |
| * 法教育推進協議会賞は該当作品なし | |
〈授賞式〉
平成26年3月25日(火)、東京高等検察庁第2会議室において、平成25年度法教育懸賞論文の表彰式が行われました。
法教育推進協議会委員等出席のもと、笠井正俊 法教育推進協議会座長、中井幹晴 日本司法支援センター情報提供課長、松澤三男 商事法務研究会代表理事専務理事から受賞者に賞状及び副賞が贈られました。
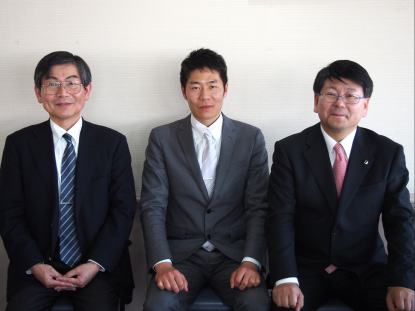
今年(平成25年度)も法教育懸賞論文を募集します。
募集は締め切りました
法教育の更なる充実・発展のため、法教育に関する論文の募集を行い、優れた論文に対して賞状及び副賞を贈呈します。
| 応 募 資 格 | 制限はありません。個人でもグループによる共同執筆でも応募できます。 |
| 論文のテーマ | 私とみんなの法教育 -具体的な授業例を踏まえて- |
| 応 募 要 領 | ○論文は日本語で作成され、未発表のものに限ります。
○論文は、ワープロで作成する場合は、活字12ポイント横書き1頁34字×30行のA4判用紙(特定の学校や機関名等の入ったものは不可)を使用し、枚数は4ページ以上、6ページ以内とします。 手書きの場合は、市販のA4判横書き用400字詰め原稿用紙を使用し、黒又は青インクの万年筆又はボールペンを使用して記載(鉛筆書きは無効)することとし、枚数は、同原稿用紙10枚以上16枚以内とします。いずれも、字数を超えるものは、減点の対象とします。 なお、統計表、グラフ等を用いる場合も指定枚数以内に収まるようにしてください。 ○法教育の授業例については、少なくとも、対象学年のほか、「①目標」、「②内容」、「③方法」及び「④法教育の授業を実践しての感想や苦労した点及び法教育授業の在り方についての考察・意見」の4項目については記載してください(その他記載すべき項目について指定はありません)。 また、当該法教育の授業を受けた児童・生徒がどのような感想を持ったか、どのように発達したかが分かる「法教育の授業を受けた児童・生徒の感想文」(市販のB4版縦書き用400字詰め原稿用紙等により1枚程度で、児童・生徒の自筆のものに限る)を必ず1通以上添付するほか、必要に応じて、教材、学習指導案、授業で使用した資料及び児童・生徒に配付したワークシート(以下「教材等」という)を添付してください。教材等については、自作又は他作を問いませんが、自作以外の場合は、作成者、出典を(一部変更の場合はその旨も)必ず明記してください(児童・生徒の感想文及び教材等はイの分量には含まれません)。 なお、本コンクールにおいて論文及び感想文を公表する際には、児童・生徒の氏名の公表の可否について別途協議させていただきます。 ○論文を記述した用紙には、氏名、学校・所属団体名その他予断を生ずるような事項を記入しないようにしてください。 ○論文の提出にあたっては、論文の本文とは別に、次の書面を作成して、論文の本文に添付してください。 ・ 論文作成者(グループによる共同執筆の場合は、代表者1名(代表者と明記)及び他の全ての共同執筆者)の氏名(ふりがなを付する)、生年月日、住所、電話番号、職業・学校名等の所属団体名(任意)を記載した書面 ○著作権法に留意しつつ、すでに発表されている情報、意見、統計、グラフ等については、それに言及する際、その都度適切な出典を注記して引用し、一読しただけで、どの部分が他者から得た情報で、どの部分が独自の調査・収集にかかる未発表の情報や資料であるかが判然とするようにしてください。 ○論文の応募は、1人(1グループ)1通(1論文)とします。なお、応募論文・感想文及び教材等は、返却いたしません。 |
| 提 出 期 限 | 平成25年11月29日(金)(必着厳守) |
| 提 出 先 | 法務省大臣官房司法法制部司法法制課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 (封筒表面に「懸賞論文」と朱記) |
| 賞及び賞金 | 優れた論文には、次の各賞に応じ、それぞれ賞金が授与されます。
なお、受賞者に対する表彰式を法務省において開催し、法務大臣からの表彰状授与を予定しております(同表彰式には、論文作成者のほか、添付いただいた感想文を書いた児童・生徒の代表の方1、2名にも参加いただく予定です)。 日本司法支援センター賞 (1通) 公益社団法人商事法務研究会賞 (1通) 奨励賞(3通以内) ※ いずれの賞も該当作なしの場合があります。 |
| 論文の審査 | 法教育推進協議会法教育普及検討部会で審査を行い、その結果を法教育推進協議会に報告し、法教育推進協議会の決議を経て受賞者を決定します。 なお、過去に受賞された方が作成した論文については、受賞の対象から除外させていただきます。 受賞者の決定は、平成25年1月中旬ころに行います。ただし、審査・受賞者の決定過程に関する問い合わせには応じられません。 |
| 受 賞 者 の 発 表 等 |
受賞者の発表は、本人(グループによる共同執筆の場合は、代表者1名)に通知するほか、法務省ホームページ等において行います。 受賞論文は、法務省ホームページ等において掲載します。また、上記5により受賞の対象とならなかった論文であっても、優れた内容のものについては、法務省ホームページ等に掲載することがあります。なお、これらの論文の著作権は、法教育推進協議会に帰属することとします。ただし、教材等については、その作成者が執筆者以外の場合には、法務省ホームページ等への掲載も省略します。執筆者が、当該論文を他の媒体等で発表することを希望する場合は、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。 応募論文のアイデア、内容については、受賞したか否かを問わず、利用、公表させていただくことがありますが、その場合に、応募者に対していかなる責任も負いかねます。 |
| 主催 法教育推進協議会 日本司法支援センター(法テラス) 公益社団法人商事法務研究会 |
|
| 後援 日本弁護士連合会 日本司法書士会連合会 | |
平成24年度法教育懸賞論文受賞者の発表について
法教育推進協議会、日本司法支援センター(法テラス)、公益社団法人商事法務研究会の主催、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会の後援による法教育懸賞論文は、平成24年7月に応募を開始し、11月末日をもって応募が締め切られました。
本年度のテーマは、「学校現場において法教育を充実・発展させるための方策について-具体的な授業例を踏まえて-」でしたが、全国各地の教員、法律実務家等の皆さんから多数の応募をいただきました。
法教育推進協議会法教育普及検討部会において厳正な審査を行った後、平成25年2月8日の法教育推進協議会での決議を経て次の受賞者が選定されました。
| 【法教育推進協議会賞】 | 関根 憲一氏(豊島区立池袋中学校主任教諭) |
| 【日本司法支援センター賞】 | 小代誠一郎氏(大阪府立城東工科高等学校教諭) |
| 【公益社団法人商事法務研究会賞】 | 川端 裕介氏(八雲町立熊石第二中学校教諭) |
| 【奨励賞】 | 塩川 泰子氏(弁護士・第二東京弁護士会) |
3月21日に行われた表彰式の様子は、後日、法教育レポート等でお伝えする予定です。
〈授賞式〉
平成25年3月21日、法務省第1会議室において、平成24年度法教育懸賞論文の表彰式が行われました。
法教育推進協議会委員等の出席のもと、笠井正俊 法教育推進協議会座長、北岡克哉 日本司法支援センター総務部長(当時)、松澤三男 商事法務研究会代表理事専務理事から各賞の受賞者に賞状および副賞が贈られました。

今年(平成24年度)も法教育懸賞論文を募集します。
募集は締め切りました
法教育の更なる充実・発展のため、法教育に関する論文の募集を行い、優れた論文に対して賞状及び賞金を贈呈いたします。
| 応 募 資 格 | 制限はありません。個人でもグループによる共同執筆でも応募できます。 |
| 論文のテーマ | 学校現場において法教育を充実・普及させるための方策について -具体的な授業例を踏まえて- |
| 応 募 要 領 | ○論文は日本語で作成され、未発表のものに限ります。 ○ワープロで作成する場合は、1頁34字×30行のA4判用紙で4~6枚、手書きの場合は1 頁400文字のA4判横書き原稿用紙で10~16枚とします。 ○テーマに沿った内容を記載願います。授業例については、少なくとも、対象学年のほか、「①目標」、「②内容」及び「③方法」の3 項目は記載してください。 ○論文を記述した用紙には、氏名、学校・所属団体名その他予断を生ずるような事項を記入しないようにしてください。 ○必要に応じて、教材、学習指導案、授業で使用した資料及び生徒に配付したワークシートを添付してください。教材等については、自作又は他作を問いませんが、自作以外の場合は、作成者、出典を(一部変更の場合はその旨も)明記してください。 |
| 提 出 期 限 | 平成24年11月30日(金)(必着) |
| 提 出 先 | 法務省大臣官房司法法制部司法法制課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 (表面に「懸賞論文」と朱記) |
| 賞及び賞金 | 優れた論文には、次の各賞に応じ、それぞれ賞金が授与されます。
法教育推進協議会秀賞 (1通) 10万円 日本司法支援センター賞 (1通) 10万円 公益社団法人商事法務研究会賞 (1通) 10万円 奨励賞(3通以内) 3万円 ※ いずれの賞も該当作なしの場合があります。 |
| 論文の審査 | 法教育推進協議会法教育普及検討部会での審査の後、法教育推進協議会の決議を経て受賞者を決定します。なお、過去に受賞された方が作成した論文については、受賞の対象から除外させていただきます。
受賞者の決定は、平成26年2月頃に行います。ただし、審査・受賞者の決定過程に関する問い合わせには応じられません。 |
| 受 賞 者 の 発 表 等 |
受賞者の発表は、本人(グループによる共同執筆の場合は、代表者1名)に通知するほか、法務省ホームページ等において行います。 受賞論文は、法務省ホームページ等において掲載します。なお、受賞論文の著作権は、法教育推進協議会に帰属することとします。ただし、教材等については、その作成者が執筆者以外の場合には、法務省ホームページ等への掲載も省略します。執筆者が、当該論文を他の媒体等で発表することを希望する場合は、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。応募論文掲載のアイデア、内容については、受賞したか否かを問わず、利用、公表させていただくことがありますが、その場合に、応募者に対していかなる責任も負いかねます。 |
| 主催 法教育推進協議会 日本司法支援センター(法テラス) 公益社団法人商事法務研究会 |
|
| 後援 日本弁護士連合会 日本司法書士会連合会 | |
平成23年度法教育懸賞論文受賞者の発表について
法教育推進協議会、日本司法支援センター(法テラス)、社団法人商事法務研究会の主催、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会の後援による法教育懸賞論文は、平成23年6月に応募を開始し、10月末日をもって応募が締め切られました。
本年度は「学校現場において法教育を普及させるための方策について-法教育の授業例を踏まえて」をテーマとし、全国各地の教員、法律実務家等の皆さんから多数の応募をいただきました。
法教育推進協議会法教育普及検討部会において厳正な審査を行った後、平成23年12月26日の法教育推進協議会の決議を経て、次の受賞者が選定されました。
| 【法教育推進協議会賞】 | 春田久美子氏(弁護士・福岡県弁護士会) |
| 【日本司法支援センター賞】 | 松本榮次氏(兵庫県西宮市上ヶ原南小学校教諭) |
| 【社団法人商事法務研究会賞】 | 三浦清和氏(京都府井出町立泉ヶ丘中学校教諭) |
| 【奨励賞】 | 該当者なし |
〈授賞式〉
平成24年2月29日、法務省第1会議室において、平成23年度法教育懸賞論文の表彰式が行われました。
法教育推進協議会委員等の出席のもと、笠井正俊法教育推進協議会座長から受賞者に賞状および副賞が贈られました。
今年(平成23年度)も法教育懸賞論文を募集します。
法教育の更なる普及・発展のため、法教育に関する論文の募集を行い優れた論文に対して賞状及び賞金を贈呈いたします。
| 応募資格 | 制限はありません。個人でもグループによる共同執筆でも応募できます。 |
| 論文のテーマ | 学校現場において法教育を普及させるための方策について -法教育の授業例を踏まえて- |
| 応募要領 | ○論文は日本語で作成され、未発表のものに限ります。 ○ワープロで作成する場合は、1頁34字×30行のA4版用紙で4枚以上、6枚以内、手書きの場合は1 頁400文字のA4版横書き原稿用紙で10枚以上、16枚以内とします。 ○法教育の授業例を踏まえて、学校現場において法教育を普及させるための方策について記載願います。法教育の授業例については、少なくとも、対象学年のほか、「①目標」、「②内容」及び「③方法」の3 項目については記載してください。 ○論文を記述した用紙には、氏名、学校名等の所属団体名その他予断を生ずるような事項を記入しないようにしてください。 ○必要に応じて、教材、学習指導案、授業で使用した資料及び生徒に配付したワークシートを添付してください。教材等については、自作又は他作を問いませんが、自作以外の場合は、作成者、出典を(一部変更の場合はその旨も)明記してください。 |
| 提出期限 | 平成23年10月31日(月)(必着) |
| 提出先 | 法務省大臣官房司法法制部司法法制課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 (表面に「懸賞論文」と朱記のこと) |
| 賞及び賞金 | 優れた論文には、次の各賞に応じ、それぞれ賞金が授与されます。
法教育推進協議会秀賞 (1通) 10万円 日本司法支援センター賞 (1通) 10万円 社団法人商事法務研究会賞 (1通) 10万円 奨励賞(3通以内) 各 3万円 ※ いずれの賞も該当作なしの場合があります。 |
| 論文の審査 | 法教育推進協議会法教育普及検討部会で審査を行い、その結果を法教育推進協議会に報告し、法教育推進協議会の決議を経て受賞者を決定します。受賞者の決定は、12月下旬ころに行います。ただし、審査・受賞者の決定過程に関する問い合わせには応じられません。 |
| 受賞者の 発表等 |
受賞者の発表は、本人(グループによる共同執筆の場合は、代表者1名)に通知するほか、法務省ホームページ等において行います。 受賞論文は、法務省ホームページ等において掲載します。なお、受賞論文の著作権は、法教育推進協議会に帰属することとします。ただし、教材等については、その作成者が執筆者以外の場合には、法務省ホームページ等への掲載も省略します。執筆者が、当該論文を他の媒体等で発表することを希望する場合は、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。応募論文掲載のアイデア、内容については、受賞したか否かを問わず、利用、公表させていただくことがありますが、その場合に、応募者に対していかなる責任も負いかねます。 |
| 主催 法教育推進協議会 日本司法支援センター(法テラス) 社団法人商事法務研究会 |
|
| 後援 日本弁護士連合会 日本司法書士会連合会 | |
平成22年度法教育懸賞論文受賞者の発表について
法教育推進協議会、日本司法支援センター(法テラス)、社団法人商事法務研究会の主催、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会の後援による法教育懸賞論文は、平成22年6月に応募を開始し、10月末日をもって応募が締め切られました。
本年度は「学校現場において法教育を普及させるための方策について」をテーマとし、全国各地の教員、法律実務家等の皆さんから多数の応募をいただきました。
法教育推進協議会法教育普及検討部会において厳正な審査を行った後、平成22年12月22日の法教育推進協議会の決議を経て、次の受賞者が選定されました。
| 【最優秀賞】(1名) | 武藤立樹氏(島根県立隠岐島前高等学校教諭) |
| 【優 秀 賞】(2名) | 春田久美子氏(弁護士・福岡県弁護士会) 札埜和男氏(京都教育大学附属高等学校教諭) |
| 【佳 作】(4名) | 長島光一氏(明治大学付属明治高等学校講師) 松岡正志氏(弁護士・広島弁護士会) 飯野眞幸氏(前・群馬県立高崎女子高等学校長) 金子幹夫氏(神奈川県立三浦臨海高等学校総括教諭) |
「法と教育学会」について
法律界と教育界の架橋となる「法と教育学会」が設立されました。
小・中・高等学校における法教育、大学法学部における法学教育、法科大学院・司法研修所における法曹教育、そして法律専門家に対する研修・教育のあり方について総合的に研究し、
それを教育の現場で実践するため、法学、教育学またはこれらの関連分野における研究
もしくは実務に携わる方の研究上の連絡・協力を促進することを目的とした学会です。
入会手続等の詳細については、法と教育学会ホームページをご覧下さい。

 詳細はこちらのチラシをご覧ください
詳細はこちらのチラシをご覧ください