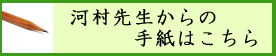高校教諭と労働法学者の往復書簡(4) 「解雇規制」
河村先生からのお手紙に対する荒木先生の返信です。
(右上の文字サイズを「中」にしてご覧ください)
お便り有り難うございました。7月になって大変な猛暑ですね。盆地熊本で育ち、酷暑には慣れているはずの私もいささかバテ気味ですが、先生にはお変わりありませんか。
■ 最低基準と労働者の同意
今回は、先月の議論のフォローアップから始まっていますね。労働基準法や最低賃金法の定める労働条件の最低基準が、交渉力に劣る労働者の同意を修正して書き換える(その限りで契約の自由を修正する)点に、労働法が民法(市民法)とは異なる新たな法領域として登場した意義があることの確認は非常に有益だと思います。
教材プリントでは、労基法13条が引用されていますが、その場合には、労基法上の規制(例えば労基法32条の1日8時間労働の規制)の設例を示し、あるいは今回のように最低賃金を下回る合意の議論をする場合には、引用する条文も最低賃金法4条2項の「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」とされると、よりわかりやすいかもしれません。
それから、今回の最低賃金の例で議論する場合の(1)の文章は、例えば「労働者が、最低賃金法に基づいて設定された広島県の719円に満たない650円で働くことに同意したとき、(①労働者は650円以上は請求できない、②労働者は719円を請求できる、③労働者が719円を請求するなら、それは合意した内容と異なるので使用者は雇用契約を解消できる)」とされてもよいかもしれません。一方当事者(ここでは労働者)が合意した契約条件は無効だとして別の条件を主張する場合、他方当事者(使用者)は、それなら契約自体、有効に成立していないと主張することも考えられるのですが、労働基準法や最低賃金法は、そうした主張を許さず、端的に法定基準で契約を規律することを、③の選択肢を示すことで伝えられればなおよいと思います。
■ 解雇の自由とその修正
さて、今回のテーマは「解雇規制」、解雇が規制されている日本と解雇が自由なアメリカを対比して、これからの日本の雇用モデルについて考えさせようという指導案を頂きました。
民法627条では、両当事者(使用者も労働者も)が、2週間の予告をするだけで、雇用契約を自由に、つまり正当事由がなくとも、解約できるというルールを定めています。これは、労働者にとっては辞職の自由を、使用者にとっては解雇の自由を定めていることになります。この解雇の自由について労契法16条が一定の規制を加えているのですが、これを高校生に対してどう表現するかはなかなか難しい問題です。
欧州各国は解雇に正当事由を要求する規制を導入しており、まさに解雇の自由を正面から修正しています。これに対して、日本の裁判所は、そうした制定法がなく、民法に解雇の自由原則が定められた制度の下で、解雇を制限すべきかどうか悩んだわけです。
戦後、市場に過剰労働力が溢れて、解雇は文字通り生活の糧を奪うもので、労働者およびその家族に深刻な打撃を与えることに鑑み、裁判所は、解雇の自由を制約すべきだと考えました。しかし、民法が使用者に解雇権を与えている以上、正当事由がなければ解雇できないという制定法に反する解釈はできません。そこで裁判所は、民法の規定する権利濫用の禁止のルールに依拠して(民法の権利濫用禁止規定は日本国憲法制定前より存在する市民法上の原則ですので、憲法12条の引用はなくてよいと思います)、解雇が客観的合理的理由を欠き、社会的に相当と認められない場合には、解雇権を濫用したものとして、解雇は無効となるという解雇権濫用法理を形成していきました。つまり、日本の判例法理は、使用者に解雇の自由があること自体は正面から否定はせず、ただ、その権利行使が濫用となる場合を広く捉えて、事実上、解雇権の行使に厳しい制約を課していきました。この判例法理が、2003年の労基法改正で初めて法律上の条文となり、2007年に労契法16条に移行されて現在に至っています。
したがって、「労働法は解雇自由の原則を修正して」というのは事実上はそうなのですが、法律上はなお解雇自由の原則は維持されているとも言いうる微妙な問題があります。「労働法は、権利の濫用は許さないという民法の原則を活用して、解雇権の自由な行使に制限を加えた」といった文章がより穏当かもしれません。しかし、以上の議論は、研究者の間でなされるべきもので、高校生に対しては、労働法が解雇の自由を制限している、ということで話を進められて結構だと思います。
なお、非正規労働の問題は、おそらく別の機会に独立して取り上げるべき重要性がありますので、今回は、割愛されてもいいかもしれませんね。
■ 解雇規制の論じ方
さて、今回の中心課題は、解雇の自由を制限する雇用システムと解雇の自由を認める雇用システムのそれぞれのメリット・デメリットを生徒達に自由に議論させ、これからの雇用システムの望ましい方向について考えようというものだと思います。少し気になったのは、教材プリントの日本の雇用モデルおよびアメリカの雇用モデルの説明だと、職業訓練の相違、契約における職務・勤務地の限定の有無、企業の解雇に対する考え方の相違が、結果として日本の解雇制限、アメリカの解雇自由という規制の違いをもたらした、という因果関係にあるかのような印象を与える点です。これも解雇規制の一面を正しく指摘しているものではありますが、解雇規制のあり方が、職業訓練のあり方、契約のあり方、労使関係のあり方、そして雇用システムそのものを規定するという逆の関係も重要です。
日本で解雇権濫用法理の形成期には、未だ長期雇用システムや長期雇用を前提とした人事管理等も存在しませんでしたが、裁判所は、不当な解雇を、労働者保護のために権利濫用として無効としていきました。そして、解雇権の自由な行使に判例法理が制約をかけていったことが、日本の雇用管理にも影響して、安易な解雇を避け、雇用を尊重する長期(終身)雇用システムの形成の一因となったといってよいでしょう。もちろん長期雇用システムの形成には、解雇権濫用法理以外の要因、例えば、解雇に反対する労働組合運動や、高度成長期における人材不足、国を挙げての雇用維持尊重の雇用政策の展開等も、大きく作用しています。長期雇用システムがどのような要因によって形成されたかについては、研究者の間でも議論のある問題ですので、ここではその問題に深入りすることは避けて、むしろ、解雇が自由な雇用システムと解雇を制限する雇用システムがあるとして、それぞれの雇用システムに、どのようなメリットとデメリットが考えられるか、そこではどのような社会が形成されるか、を生徒達の柔軟な頭で考えてもらうことが、より有益であるように思います。
■ 解雇制限のある雇用システム
近時、日本では解雇が制限されているために、経済に悪影響が出ているという指摘が聞かれます。マクロレベルでは、産業構造が大きく変化すべき現代において、解雇が制限されている結果、衰退産業から新興産業への労働移動が制限され、日本の産業活力を阻害している、ミクロレベルでは企業内で有効に活用されない労働者が解雇制限の結果、滞留してしまい、企業にとっても労働者にとっても不効率な事態が生じている、解雇が制限されているために、企業は解雇以外の方法で労働者が自ら退職するように、陰湿な措置をとることを誘発しており、これは健全なことではない、等の指摘があります。なお、本来、解雇規制については、使用者側の経営上の事由による解雇と、労働者側の事由による解雇とを区別して論ずべきですが、ここではこれ以上立ち入らずにおきます。
雇用保障を重視する長期雇用システムは、伝統的には終身雇用制といわれたように、定年まで勤めることを前提に、使用者の賃金支払いと労働者の貢献の収支がバランスするような制度でした。終身雇用制度とセットで採用されていた年功賃金制度では、若いときには労働者の貢献よりも企業の支払う賃金が低い関係にあり、40歳台以降になると、この関係が逆転し、貢献よりも高い賃金が支払われ、定年時に双方の収支がバランスするような制度として運用されてきました。しかし、労働者が多様化し、パートタイムや有期契約で働くもの、正社員でも、一時的にパートタイムに転換する者、一定期間休職、あるいは、修学、起業等、労働者ではない地位に立つ者、さらには、そもそも一定期間しか日本で就労しない外国人労働者など、多様な人が多様な働き方をするようになってきています。そうしたときに、定年までフルタイムで勤めることで収支が合うという終身雇用モデルは、決してすべての人にとって合理的なものとはいえなくなってきています。
そして、雇用保障(解雇制限)のある雇用システムは、無期契約で雇用されている正社員を念頭においていましたが、正社員の雇用保障が、非正規労働者の犠牲の上に守られているとするなら、より強いものが守られ、本当に保護すべき弱者が保護を享受していないのではないか、という側面についても真剣に考えてみる必要があるでしょう。
労働者保護のために解雇を制限するという考え方に対しては、むしろ解雇を自由にすることにより、流動的な労働市場、転職しやすい社会が形成され、転職できるということが、実は、個々の労働者が会社に対して自分の主張を堂々とぶつけることでき、個々の労働者の交渉力を高めることになる、という見方もあります。この立場に立つと、解雇制限は転職しやすい社会の形成を阻害し、労働者の交渉力にも悪影響があることになります。
■ 解雇自由の雇用システム
では、解雇が自由な(雇用保障のない)アメリカのような雇用システムはどうでしょうか。解雇が自由な雇用システムでは、労働者はいつ解雇されるかわかりませんから、その企業でだけ役立つような知識や技術の習得には熱心に取り組みません。そして、長期的な雇用保障がなければ
、少しでも条件のよい雇用機会があれば、転職するのが合理的で、転職が当たり前の社会になるでしょう。労働者がすぐに転職してしまうのなら、使用者は費用を負担して教育訓練を行っても無駄な投資となってしまいますから、自ら教育訓練するのではなく、既に技能を備えた人を雇い入れる行動に出るでしょう。そうすると、教育訓練を担うのは企業ではなく、企業外の教育訓練機関となり、その費用は労働者自身か国等が負担することとなるでしょう。
全ての労働者が常に自分の技能を高めるために教育訓練に励もうとするかというと、生来怠惰な我が身を顧みても、なかなかそうはならないような気がします。企業が労働者の教育訓練のインセンティブを持たない雇用システムでは、一部の意識の高い労働者は別として、大多数の普通の労働者は、技術革新に取り残されて、労働者間の技能格差がますます拡大する恐れもありそうです。また、教育訓練を公的機関が行う場合、企業自身が行う場合と比べると、非効率で時代遅れのものとなる懸念もあります。
雇用保障のない雇用システムの、より大きな問題は、使用者と労働者の交渉力の格差がそのまま労働関係を支配してしまう点です。例えば、使用者が時給1000円のところ、900円に引き下げる提案をしたときに、労働者がそれは不当だと思っても、解雇が自由の雇用システムでは、賃下げ提案を拒否すれば適法に解雇されてしまいます。そして使用者は時給900円で働いてよいという求職者を雇えば済みます。労働条件調整問題も、ここでは解雇と雇い入れ(hire and fire)という市場メカニズムによって決定されることになります。労働法は様々な権利を労働者に保障していますが、それらの権利も雇用関係が存続して初めて意味をなすもので、雇用保障がないということは、雇用関係・労働法制の基礎を掘り崩す危険があります。したがって、解雇が自由という制度を維持している国はアメリカ以外の先進諸国には見当たりません。
これに対して、雇用保障のある長期的な雇用関係では、労働条件の調整が必要となると、解雇ではなく、繰り返し交渉することになります。これは経済学で言う「繰り返しゲーム」に該当し、そこでは相手を裏切って目の前の利益を得るような行動をとると、次は必ずしっぺ返しにあってしまいます。したがって、相手を裏切らずに信頼関係を維持する方が合理的な行動となります。雇用保障のない労働関係では、その場その場で、より多くの利益を相手から獲得するのが合理的行動となりますので、対立的なゼロサムゲーム(一方が利得すれば、その分、相手方は損をする関係)となりがちで、信頼関係をベースにした協力的なプラスサムゲームやウインウインゲームは展開しません。アメリカで労使関係が対決的だと言われる背景には、解雇が自由で長期的労働関係の基盤がないことも影響している可能性があります。
■ 雇用モデルの未来
以上のように、日本モデルもアメリカモデルもそれぞれに一長一短があるようです。そして、それぞれの国の労働法制も、そうした雇用モデルを前提に展開することになります。例えば、アメリカでは、解雇は自由で市場機能が労働関係にダイレクトに作用する雇用システムを構築していますが、差別については非常に厳しい規制を導入しています。性別・皮膚の色・宗教等の伝統的な人権に関わる差別禁止のみならず、年齢・障害など、より新しい差別規制も発展させています。市場メカニズムに依拠したアメリカの雇用システムなのに差別を厳格に規制することは整合するのかという疑問が生ずるかもしれませんが、市場メカニズムが効率的に機能するためのインフラとみれば、矛盾するものではありません。そして、こうした差別規制が恣意的な解雇に一定の制約をかける機能を営んでいる可能性もあります。
他方、日本では長期雇用システムが確立してからは、人事管理、労使関係も長期雇用システムを前提に展開されてきました。諸外国では、アメリカに限らず、雇用はなすべき仕事があって、そのために人を雇い入れるのが一般ですので、雇用契約上も仕事は特定されていると理解されています。そうするとその仕事がなくなれば、解雇も可能というところから出発します。これに対して、雇用を長期にわたって保障しようとする日本モデルの下では、職務も環境変化に合わせて変更することになり、契約上、労働者の職務は特定されていないという解釈が一般化することになりました。使用者に広範な配置転換の権限を与えたり、労働条件の変更権限を与えたりしているのも、それが日本の長期雇用システムに適合的だったからでしょう。このような雇用システムでは、個別の合意よりも継続的・組織的就労という側面が重視され、使用者の人事権の機能が大きくなりますが、その人事権行使の濫用や合理性をチェックする法理も発展することになります(配転命令権濫用の法理、就業規則の合理的変更法理等)。
したがって、どちらかのモデルが絶対的に正しく他方が間違っているといったことではなさそうです。むしろ、柔軟な生徒達は、自分の将来の働き方を想像した場合、次のようなことを考えるかもしれませんね。チャレンジ精神に富んだA君は、アメリカモデルがより自分が活き活きと活躍できる望ましい雇用モデルと考えるかもしれませんし、常に変化にさらされる不安定な生活をストレスと感じるBさんは、日本モデルが安定・安心をもたらすよりよい雇用モデルと思うかもしれません。C君は、若いときはバリバリと働いてチャレンジできるアメリカモデルがいいと思うけれど、子供ができてからは、あまり変化に翻弄されない安定的な日本モデルがよい、というように、自分のキャリア展開の中で違う雇用モデルを選びたいと考えるかもしれません。
各国の雇用システムは、それぞれの社会の展開の中で歴史的に形成されてきたものですので、傾向としてはアメリカモデルや日本モデルといった違いが出てきます。しかし、現在は、そうした一つの雇用モデルには収まらない多様な労働者が登場してきているようです。そうすると、労働法に要請されているのは、個々の労働者が自分が望ましいと思う雇用モデルを選択できるように、多様な雇用モデルを提供すること、そして、そこで選択した雇用モデルが、社会正義の観点から許容されるバランスの取れたものとなるように環境を整えることではないかと思います。今回先生が言及されていた日本の非正規雇用という雇用モデルについては、そうしたバランスの取れた働き方だったのかどうかが、近時問題となったのかもしれません。
またしても長いお返事になってしまいました。今回はこの辺りで失礼します。酷暑が続いております。くれぐれもご自愛を。
アーカイブ
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
カテゴリータイトル
- インタビュー (16)
- はじめに (1)
- 取材日記 (325)
- 報道から (5)
- 対談 「法学教育」をひらく (17)
- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)
- 年度まとめ (10)
- 往復書簡 (10)
- 河村先生から荒木先生へ (5)
- 荒木先生から河村先生へ (5)
- 教科書を見るシリーズ (21)
- 法教育素材シリーズ (7)