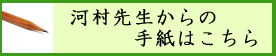高校教諭と労働法学者の往復書簡(1) 「労働法『で』考える? 労働法『を』考える?」
河村先生からのお手紙に対する荒木先生の返信です。
(右上の文字サイズを「中」にしてご覧ください)
桜に包まれた本郷キャンパスは、また新しいメンバーを迎えて華やいだ気配です。春は、手塩にかけた学生達が巣立ち、そして希望に満ちた新しい学生達を迎えるという、私たち教師にとっては、感慨一入の季節ですね。学年の変わり目のお忙しい中、お便り、有り難うございました。これから往復書簡、どうぞよろしくお願い致します。
■ 身近で切実な労働法
河村先生には、法教育の素材として労働法を取り上げて頂き、大変有り難く、また嬉しく存じます。高校生に「法」について考えてもらう場合に、労働法はとても身近に想像できる分野で、素材として好適な法分野ですね。
新聞の社会面でも労働問題は頻繁に取り上げられています。やや明るい兆しが出てきたとはいえ、昨今の厳しい雇用情勢、就職事情や傷んだ就労環境についてのニュースに接すると、働くルールを定めた労働法は、高校を卒業して社会人になろうとする生徒諸君、あるいはアルバイトをする学生にとっても、切実な関心事でしょう。
■ 「労働法で考える」「労働法を考える」と労働法の知識
さて、今回は、河村先生から、法教育として労働法を素材として取り上げる際に何を目指すべきかという問いかけを頂いたように思います。河村先生が、「(1)労働法で考える」といわれているのは、労働法という視点・視角から、社会を見ることによって見えてくるものは何か、そのことを通じて、「法」というものについて生徒に考えさせよう、という趣旨と理解しました。これに対して、「(2)労働法を考える」とは、そもそも労働法は社会に対してどのような内容のものであるべきかを、社会経済構造の変化、労働者像や労働者の価値観の変化を踏まえて、生徒に考えさせようという趣旨でありましょう。
河村先生は前者〔(1)〕の内容を「短期的視点」と「長期的視点」に分けておられます。「短期的視点」とは、割増賃金がいくらになるかを計算できる、そういう実践的な知識や手段を伝えることに主眼を置いた教育をさしているようです。これに対して、「長期的視点」とは、なぜ割増賃金が発生するのかを説明できること、つまりなぜそのような労働法上の規制があるのか、について考えさせ、規制の存在理由を探ることで、法と社会、そこに登場する労働者という人間像について考えさせようという趣旨でしょう。
先生の問題提起については、「(1)労働法で考える」というスタンスの中で「短期」「長期」という二つの立場を考えるより、「短期的視点」による教育は、「(0)労働法を知る(労働法知識を得るための)法教育」と位置づけるのがわかりやすいように思いました。確かに、社会で働く者が、自分たちの労働者としての権利を認識し、自らの身を守るためにその権利を正当に行使できるようになることは非常に重要なことです。
しかし、河村先生は、法教育の素材として労働法を取り上げる場合、そうした知識の伝達を中心に据えることでよいのだろうかと疑問をお持ちのようです。おっしゃるとおり、単なる知識は、変化の大きな現代においては、すぐに陳腐化し、使えなくなってしまいます。例えば、1947年に制定された労働基準法は女性の深夜業を一律に禁止してきました。しかし、男女雇用平等の理念から、女性という理由で深夜業を禁止することが本当に女性の保護に資するのか、むしろ男性と対等に働き、職業能力を発展させる機会を奪っているのではないか、という疑問が生じました。そこで、女性の深夜業禁止は、1985年の男女雇用機会均等法制定によって緩和され、1997年の均等法改正で撤廃されることになりました。
このように、今、労働法がどのような保護を与えているかという知識の伝達は、実践知としては重要ですが、高校の法教育という場で、それだけ(それが中心)でよいのか、という先生の疑問に私も深い共感を覚えます。まさに、なぜそのような規制が必要とされ制定されたのか、その規制の基礎にある社会認識あるいは労働者の価値観はどのようなものだったか、そうした認識は現在でも妥当するのか等を問うこと、深夜業禁止についていえば、なぜかつては禁止されていたのに、現在では解禁されたのかを問うことにより、法と社会の関係を考えることが、法教育にとっては重要だと思います。
もちろん、(1)労働法で考えたり、(2)労働法を考えるためには、労働法の現在の規制内容についての知識・認識は必要です。しかし、それを覚えることを目的とするよりも、以下のような事項に及ぶ授業の方が、魅力的ですし、ずっと将来に残るものになると思います。
■ 労働法で考える:労働法的視点から見た社会・合意・契約
さて、「(1)労働法で考える」という際には、労働法がなぜ市民法(民法)の処理を修正する新たな法分野として登場したのか、ということに触れることになるでしょう。
割増賃金を例にとりますと、時間外労働を行った場合、労働基準法は2割5分増しの割増賃金を支払うことを要求しています。では、就職面接で、企業の社長さんから「我が社は、割増賃金を当てにしてダラダラ働くような社員はいらない。時間など気にせずにバリバリ働きたいという人に来てほしい。」といわれて、就活をしていた学生が、「もちろん、割増賃金なんかいりません、労働時間とか関係なく御社でバリバリ働かせてください。」といって就職をしたとしましょう。この新入社員は、割増賃金は不要だという約束をして入社したのだから、社長は割増賃金を払う必要がない、ということになるか、というとそうはなりません。労働法は、たとえ脅されたり、騙されたりして合意した(この場合は、民法でも合意の効力が否定されます)のではなくても、労働者と使用者の交渉力の違いに着目して、法の許容する範囲をはずれた(最低基準に反する)合意を無効とし、法の基準で置き換えるところにその特質があります。「約束は守られねばならない」というのが契約法(民法・市民法)の基本ですが、「約束したから仕方がない、守るしかない」という帰結を修正するために労働法が必要とされ、登場したこと、この理解が、まず大切ですね。
最近、労働者を使い潰すような働かせ方をする企業が「ブラック企業」と呼ばれて話題になっています。労働者が入社の際に「割増賃金はいらない、時間を気にせず働くって約束したから仕方がない」と、悲惨な就労状況を我慢するといった事態も生じているようです。でも、労働法はまさにそうした使用者と労働者の間にある実際の交渉力格差を直視し、形式的な合意があっても、それをそのまま絶対視せずに、労働者の保護を図ろうとしているわけです。
そして、労働者と使用者のように交渉力に格差のある市民同士の関係は、他にも存在します。その一つが消費者契約関係です。したがって、消費者契約法でも、情報量・交渉力に劣る消費者を保護するために、法が介入して、合意の効力を修正するというアプローチを採っています。
このように「(1)労働法で考える」ことで、対等な市民同士の契約に国家は介入しないという契約自由の原則は、現実には対等たり得ない市民間の契約については、修正されてしかるべきであるという、もう一つの重要な法の考え方(社会法的考え方)の存在を認識することになるでしょう。
■ 労働法を考える:社会変化の中で労働法を見直す立法論
先生はさらに、「(2)労働法を考える」というアプローチも提起されています。これは難問です。(1)についてお話ししたように、労働法は、労働者が法の保護はいらないと言っても、それは交渉力がなくて押しつけられた合意に違いない、だから、そんな合意の効力は認めずに法の定めた保護を貫徹する、というのが伝統的な労働法のスタンスでした。1日8時間を超えて働かせてはならないという労働時間規制は、違反に罰則があります。したがって、労働者が労働時間規制はいらない、8時間以上働きたいと言っても、使用者に罰則がかかるとすれば、使用者はそれを禁止することになります。
そうすると、すぐに次の疑問が出てくるでしょう。女性の深夜業が禁止されていたときに、そんな規制はいらない、むしろ男性と同じように働かせてほしいという女性がいたように、割増賃金や労働時間規制はいらない、むしろ、それらの規制にとらわれずに自由に働かせてほしいと本当に思っている労働者もいるのではないかと。例えば、iPS細胞を使って難病の治療を可能とする技術や薬を開発している企業や大学の研究者・技術者達は、純粋に時間に関係なく、そうした技術や薬を開発する仕事に没頭したい、そして世の中の役に立ちたいと思っておられるかも知れません。
実は、労働基準法の労働時間規制は1987年に大改正され、「裁量労働制」という新しい制度を導入しました。これは、業務の遂行方法や労働時間について自分の裁量で決められるような労働者(典型的には研究開発に従事する労働者等)に、実際に働いた時間に関係なく、例えば8時間働いたものとみなすこと(みなし時間制)を可能とし、実際上、労働時間規制に縛られることなく働くことを許容する制度です。大学の教員・研究者はこの裁量労働制で、労働時間を気にすることなく研究に従事することができています。
でも、また、次の疑問も生じるでしょう。時間を気にせず長時間労働をして、過労死で亡くなってしまった方もおられます。本人が構わないからといって長時間労働を許容してしまっていいのかでしょうか。過労死に至らなくても、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活のバランス)を無視して、仕事ばかりという働き方自体を見直す必要はないのでしょうか。仮に、研究者について時間にとらわれない働き方を認めるとして、バリバリ働きたいという新入社員にも同じことを認めていいのでしょうか。
次々にわき上がってくるこのような疑問は、一言で言うと労働者の多様化に起因するもののように思えます。先生が指摘されているように、古典的な労働法は、交渉力が弱く、使用者の指揮命令に拘束されて労働力を提供する「均質な」労働者像を前提としていました。でも現在は、労働者はこういうものだ、と単一のモデルで捉えることができなくなっています。そうしたときに、法の規制はどうあるべきなのでしょうか。
「(2)労働法を考える」ということは、労働法の規制は今後どうあるべきかという「立法論」を扱うことになります。女性の深夜業禁止の解除にしても、裁量労働制という新たな働き方の許容にしても、いずれも法改正という立法作業によって実現されたものでした。換言すると、これらのことは法改正なしに解釈論としては不可能なことでした。
立法論は、社会の実態の正確な認識と、その実態で是正すべきものは何かの探求、その是正の手段としてどのような方策が適当かの検討(法規制以外にも様々な手法があり得ます)、そして、法規制を行うべきとなった場合の具体的な法制度の選択・設計、といったことを踏まえる必要があり、大変難しい作業となります。ですから、答えはこうだ、と簡単に正解を示すことは難しいでしょう。でも、この(2)の問いを発することで、労働法の規制は固定化された所与のもの、不変のものではなく、変化する社会のありよう、そこに生きる人々の実像を踏まえて、法規制が社会正義を実現するために有効な手段たりえているのかを常に検証し、必要があれば改正の対象ともなりうること、が伝わるのではないでしょうか。(2)の視点は、法と社会の関係を考える貴重な問いかけになると思います。
先生の問いかけを頂き、私なりに、(0)労働法を知る、(1)労働法で考える、(2)労働法を考える、と整理してみました。改めて考えますと、法教育において(0)(1)(2)はいずれも必要で、相互に関連している事柄であるようです。その力点の置き方は違ってよいと思いますが、先生の問いかけが、法教育としては(0)だけに留まらず、(1)(2)に及ぶべきではないかというものだったとしますと、私はそれには全く賛成だということになります。
随分長いお返事になってしまいました。先生のお便りには、今回のお返事では十分にお応えできなかった沢山の問いが残されています。これらについては、また後日触れることができればと思っています。
アーカイブ
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
カテゴリータイトル
- インタビュー (16)
- はじめに (1)
- 取材日記 (325)
- 報道から (5)
- 対談 「法学教育」をひらく (17)
- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)
- 年度まとめ (10)
- 往復書簡 (10)
- 河村先生から荒木先生へ (5)
- 荒木先生から河村先生へ (5)
- 教科書を見るシリーズ (21)
- 法教育素材シリーズ (7)