「法学教育」をひらく(第3回) 仲正昌樹先生 現状編2
〈法学の学説と教科書について〉
大村:「先生の本で面白いのは、学説と教科書について、ある観点から述べておられることですが、そこをもう少しお話しいただけますか?」
仲正:「法学の教科書は他分野に比べて、入門書的なものでさえ、既に学説の対立について言及されているということがあります。他の分野では、学説の対立を記述するのは、上級者向けの教科書ではないでしょうか。講談社メチエから出ている八木沢敬先生の『分析哲学入門』という3冊のシリーズがあります。「分析哲学」と言っている時点で、「哲学」一般への入門から見てかなり専門化しているわけですが、初級編(と受けとれる1冊目)は実際、分析哲学で扱われている諸テーマをある程度具体例に即しながら紹介していくというスタイルなので、主要な学者の名前とその基本的な主張に少し触れているくらいで、学説対立はほとんどクローズアップされません。中級編になって、一部の問題で学説の対立があることが部分的に紹介され、上級編になって、ようやく学説の対立状況が本格的に出てきます。この上級編は、修士課程に入る前後の、これから本格的に分析哲学をやろうかという人に対して、テーマを絞り込んだうえで、最新の理論状況への見通しを与える、という性格のものではないかと思います――かなり強い意欲をもった院生向けだとは思いますが。私の感覚だと、哲学とか文学等の他の文系の分野で、本格的に学説の対立状況を把握しておく必要があるのは、大学院に入ってからです。
西欧諸国でも法典や基準となる判例がなかった時代に、学者の呈示する学説が判決のガイドラインになっていた、という歴史的経緯があることと関係しているのかもしれません。そういう状況では、将来法律の専門家になろうという人向けの教科書に、学説の対立状況を詳しく書いて、実状を知らせるのは当然のことだと思います。しかし、実定法が立法を通して体系的にされている今日では、法を体系的に解釈し、統一性を与える役割の主たる担い手は、裁判官を中心とする実務家であり、少なくとも法学者自身もそう考えているわけですから、事情はまったく異なります。学者の実務的な役割は、現在の実定法ではカバーできない類型の問題があることを学説を通して示唆することへと縮小している、ポジティヴな言い方をすれば、シフトしているのではないでしょうか。無論、そうした問題提起的な意味での学説とは異なった意味での学説、判例の意味を理論的・教育的に明らかにするための学説や、学者同士の立場の違いを明らかにするための学説も教科書の中で紹介されていて、それはそれで意味があると思いますが、どういう目的のための「学説」かきちんと定義したうえで教えているわけではないような気がします。」
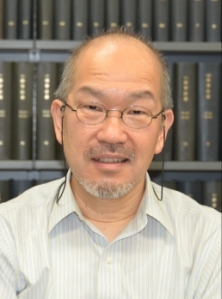 大村:「とても大事な指摘だと思います。「学説」というものが法学の中で一定の割合を占めているが、それは何なのか?先生の本ですごく面白かったのは、「学説には3種類ある」というところで、学者仲間内向け・実務家向け・学生向けの3つが挙げられています。学説は誰に向けて、何のために言われているのか明らかにする必要があるということですね。歴史的に言うと、学説は法源性のあるものとして使えるという時代がありました。現在でも、実定法上の解決が不明の問題について、学説に共通の見解があれば、学説が暫定的に通用するということがあります。それはいいけれども、多種多様な個人的な意見は「見解」と言ったらどうかと、本の中で言っておられますね。私は、個人的な意見はopinionsであり、判例と対峙する学者たちの共通の見解を単数でdoctorineと呼ぶべきだと考えており、学生に対してはopinionsは覚える必要がないと言ってやればいいと思います。
大村:「とても大事な指摘だと思います。「学説」というものが法学の中で一定の割合を占めているが、それは何なのか?先生の本ですごく面白かったのは、「学説には3種類ある」というところで、学者仲間内向け・実務家向け・学生向けの3つが挙げられています。学説は誰に向けて、何のために言われているのか明らかにする必要があるということですね。歴史的に言うと、学説は法源性のあるものとして使えるという時代がありました。現在でも、実定法上の解決が不明の問題について、学説に共通の見解があれば、学説が暫定的に通用するということがあります。それはいいけれども、多種多様な個人的な意見は「見解」と言ったらどうかと、本の中で言っておられますね。私は、個人的な意見はopinionsであり、判例と対峙する学者たちの共通の見解を単数でdoctorineと呼ぶべきだと考えており、学生に対してはopinionsは覚える必要がないと言ってやればいいと思います。
他方、実定法は体系が整っているように見えますが、しかし法律と判例だけで自足して存在するかというと、必ずしもそうでない。判例は限られた事柄についての判断なので、それを一般命題として法体系の中に組み込むには解釈が必要になります。そうすると、法体系の整合性を保持するための学説も必要になります。このような意味での学説がないと、法を了解可能な形で認識することは困難なので、教育のためにも学説は意味をもっています。それをあまり「学説」とは言っていませんが、ここで行われていることがかなり大事で、これにより学生の考え方が方向づけられることがあります。ただし、これは1つの法の見方であって、別の見方もあるということも示した方がいいということがあります。以上のように、「学説」がどういう性質のものなのかということを明らかにしてやれば、少なくとももう少し見通しはよくなる。先生のおっしゃるのもそういう趣旨ですね。」
仲正:「そうですね。」
大村:「現在の状況を根本的に再考して、現状を批判し新しいやり方を考えるタイプの「学説」もあると思いますが、それは自然科学とは少し違う意味で、「理論」と呼ばれていることがあります。これはこれでそういう性格のものだと示してやった方がいい。法学には「学説」と称する異質のものが多過ぎるという印象をおもちなのですね。」
仲正:「そういうことです。」
〈法学の学説の積極的な面〉
大村:「ところで、最近の法学部生には「学説離れ」が目立つように見受けられます。ともかく制定法と判例を理解していればいいと思っている。ただ、いくつかの箇所では判例がなく学説が大事なので、それは覚えなければいけない。しかし、判例が多くなれば学説はいらないという態度が、蔓延しつつあるようです。先生から見て、学説が法学の世界に様々な形で存在することについて、積極的に評価できる面をお話しいただけないでしょうか?」
仲正:「判例とは異なる解釈を法の本質論に基づいて呈示するという形で、現状が変更される可能性があることを示唆する学説を教える意味はあると思います。ただ、体系的に判例を理解することの重要性を理解した上でならともかく、ほとんどの学生が、学説を権威があってありがたいものとしか思っていないようでは、意味がないと思います。大村先生が今言われたようなことを、最初からちゃんと時間をかけて学び、理解したうえで先に進むのならいいと思いますが、そういうことを徹底してやる時間がないまま、実定法の授業の中でいろいろな学説が次々と出てくると、ごちゃ混ぜになってしまうと思います。よほど法学的なセンスがあるような学生以外は。
なので、主要条文をめぐる学説を全部消化していくのではなくて、マスコミでも話題になっているような大きな問題について、その問題が生じてくる法理論的な文脈や、解決のための提案を呈示する学説に絞って集中的に、紹介していく方がいいのではないかと思います。その存在意義をよくわからないまま与えられた学説を、自分に知識があることを証明してくれる御墨付きか呪文みたいに使う学生がいると思いますが、初心者にそんなものを与えていいのでしょうか。詰め込んでたくさん与えると、おもちゃのアイテムにしかならないので、そういう観点からも、ピンポイントに絞って紹介した方がいいのではないかと思います。
そういうことを考えると、全国の大学でほとんど同じフォーマットの教科書で教える、今のやり方には無理があると感じます。大学の実情に合わせて、中身を調整して教える必要はないのか、と思います。」
大村:「私は学説を素材として、現にある法を批判するという観点を磨いていくことを考えていけないだろうかと感じ始めていますが、それについて何かお考えを伺えますか?」
仲正:「本来、学説はそういう使い方をすべきだと思います。今の実務の考え方ではどうして納まりが悪いのか、真剣に議論するのであれば、学説は有効なツールになると思います。当然、本気でやれば、そこで相当時間を取られます。そうなると、すべての条文を対等に扱うのではなくて、各先生がここが一番大事だと思うところに十分時間を取って、あとのところは、教科書に出ているので自分で読んでおいて、という感じの授業にならざるをえないのではないかと思います。その場合、教科書も、そういうことをやりやすい作りにした方がいいかもしれません。哲学などでは、拘束力のある標準教科書のようなものはないですし、教科書を指定してもどうせ最後まで消化できないので、仕方なくピンポイントでやっていることが多いと思いますが、法学にもそういう勝手さがある程度あっていいのではないかと思います。」
大村:「おっしゃることはよくわかります。カリキュラムの均一化、体系化、オールインワンの発想が、法学を過度に枠づけていて規制してしまっているということですね?」
仲正:「そのとおりです。」
大村:「限られた時間の中で教えるとなると、最も効率的なやり方を覚える学生が出てきて、彼らが法学学習競争の勝者になっていくというイメージだと思います。法学にはそういうことを強いる面があるとおっしゃっておられるのですね。
もっともこうした面が強まっているのは、法科大学院開設以降のことであるように感じます。私が学生のころには、たとえば債権各論では契約と不法行為をやることになっているのに、ほとんどの時間を契約に費やし、不法行為は1、2回などということはそんなに珍しくありませんでした。最近の画一化の動きには歯止めをかけなければならないと思っています。」
〈法学の役割について〉
大村:「先生は、法学を教える組織におられて、法の役割や学習の意味をあるところでは肯定されていると思います。先生のお考えでは、1つの具体的な事例が、法の言語によって語られる以前の段階からどのように推移していくのかということを、入門段階で教えることが大事なのではないかということでした。そういうイメージと、そのイメージの背後にある「法とはこういうもの」、あるいは「法学はこういう役割を果たすべきではないか」ということの関係について、お話を伺えればと思います。
それとの関連で、先生の書かれているものの中で2つ印象に残ったことがあります。1つは、「法学はよくわからない中途半端な学問だけれど、その中に面白さがあるかもしれない」と書いておられます。たとえば刑法総論で、「行為」について様々な分析がされている。法学の世界で自閉していていつまでも論争を続けているが、それはそれで話として面白いものを含んでいるかもしれないとおっしゃっている。その中途半端な法学の可能性について、どうお考えになるかということです。
もう1つは、医療訴訟のお話で、医者と対峙して議論するときに、法学的なものにある程度の意義があるのではないかというニュアンスのことも書いておられます。現にある既成の法学が力をもつということではなくて、法学知のようなものがある専門領域での紛争を解していくうえで一定の役割を果たしうるのではないかということでした。この2点は、法学を可能態として展開させるとどうなるかということに結びついていると思いました。そのあたりのことをお話し下さい。」
 仲正:「哲学はいつまでもいろんな角度から議論し続けても困ることはありませんが、法学は実定法に即して答えを出さないといけません。答えを出せる範囲がある程度狭まっていて、その制約の中で考えないといけない。だから窮屈であると同時に、緊張感がある。制度と時間の制約の中で何らかの形で答えを出さざるをえないにもかかわらず、人々を納得させ、法の権威を守らないといけないから、バランスが取れた理由を見つけてこないといけません。最近、法哲学や政治哲学で、「理由」がクローズアップされていますが、法における「理由」の機能を考えることは、すべての法学を学ぶ人にとって重要だと思います。
仲正:「哲学はいつまでもいろんな角度から議論し続けても困ることはありませんが、法学は実定法に即して答えを出さないといけません。答えを出せる範囲がある程度狭まっていて、その制約の中で考えないといけない。だから窮屈であると同時に、緊張感がある。制度と時間の制約の中で何らかの形で答えを出さざるをえないにもかかわらず、人々を納得させ、法の権威を守らないといけないから、バランスが取れた理由を見つけてこないといけません。最近、法哲学や政治哲学で、「理由」がクローズアップされていますが、法における「理由」の機能を考えることは、すべての法学を学ぶ人にとって重要だと思います。
現実的な制約の中で、完全ではないが、最低限の正当化可能性を探究しないといけない。それは、哲学や文学にはない緊張感です。哲学や文学は、あらゆる可能性を考えて、思考の幅をどんどん広げていき、自らルールを構築していくところが面白いわけですが、法学のように、いろんな種類の制約の中で、付随的な帰結も考慮に入れながら、最適な答えを出し、その正当性を公共的に受け入れ可能な理由によって説明しないといけない。法解釈がそういう意味での緊張感を伴うものであることを、教える側だけでなく、学ぶ側も自覚し、自分たちの思考を制約している条件について落ち着いて考える機会を随時設ければ、面白く学べると思います。法の「権威」を受け入れることが、当事者にとって、社会全体にとってどういう意味をもつのか考えることで、法の理解に深みが出てくると思います。そういう学び方ができる学問であることを、法学を教えている人たちが自覚的に強調すれば、法学のイメージは変わってくると思います。
医療訴訟に多少関わったおかげで、私が学べたことを、法教育に関連付けてお話ししますと、医療訴訟というのは、専門的な知識がないと何が問題になっているのかさえ把握しにくい、科学の問題に、「法」がどう関わるべきかを考えるテスト・ケースになるのではないか、と思います。医療訴訟についてよく知らない人は、医学的専門知識が壁になることを過剰に意識しがちですが、代表的な医療訴訟とされているもので争点になっているのは、医学的事実それ自体ではなく、その事実をめぐる「合意」です。医学的事実をめぐって、医師と純科学的論争をする必要があることは稀です。インフォームド・コンセントが争点になる場合はまさにそうですが、狭い意味でのインフォームド・コンセントの事例に限らず、医療訴訟の本質は、医師が自らの医学的知識を治療に際して適切に応用したのか、つまり、思いつきや自分だけの都合によってその知識を利用したのではなく、他者が納得できるようなルールや理由に基づいて判断し、行為したのかを明らかにするところにあると思います。広い意味での合意の問題です。どういうルールに基づいてお互いの行為を規制しながら合意を形成すべきか考えるのは、法学者が一番得意とするところのはずです。治療や医学研究のプロセスには、法的に明示されたルールがなく、当事者の自発性や裁量に任せざるをえない面も多いわけですが、民事訴訟では元々法律ではっきり決まっていない問題に対して、法的に「正しい答え」を探究することが多いわけですし、対等な人間同士の合意形成はどうなされるべきか、どういう状況でどういう立場にある人が、他の当事者に対してどういう責任を負うべきかについての、「法」の基本的な見方を自分の内に確立していれば、当該の医療行為の一連のプロセスに問題があったのか、あったとすれば、どういう問題なのか的確に指摘できるはずです。医療訴訟では、医師の側が、自分の得意なフィールドである医学的事実の領域へと議論を誘導していこうとする傾向がありますが、患者側の弁護士さんや裁判官がちゃんと状況を把握していれば、そういう戦術にはひっかからないで、本来の法的な争点にきちんと引き戻せます。判例や準備書面を見ただけでは、そうした争点形成をめぐる駆け引きまでわからないと思いますが、1つでもいいから実際のプロセスをじっくり勉強するような授業があったら、法学的なものの見方とはどういうものか、イメージを掴めるのではないかと思います。」
大村:「今のお話を最初のお話と結び付けたいと思います。法学は制約のもとで議論をしているとおっしゃられましたように、暫定的な議論の仕方があることが大事だと思います。一方で、訴訟を解決するときに、様々な制約があっていつまでも議論を続けられない場合がある。それは訴訟に限らないのでこのやり方には汎用性があると思いますが、法的なものの考え方には、訴訟を一つのモデルにして理解することを通してでないと、獲得できないものがあると思います。他方では、合意とは何なのかということは必ずしも訴訟には直結しないと思います。法学者が合意や所有権をどう考えてきたか、それらについて法学的に考えるとどういうことになるかをしっかり勉強していれば、自分たちがいろいろなことに対処する際に役立つはずだとおっしゃっているように思います。」
来週公開の展望編へつづく
改訂版〈学問〉の取扱説明書 |
||
 |
著 者 判 型 頁 数 発行年月 定 価 発 行 |
仲正昌樹 著 四六判 398頁 2011年4月 1,800円(税別) 作品社 |
アーカイブ
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
カテゴリータイトル
- インタビュー (16)
- はじめに (1)
- 取材日記 (325)
- 報道から (5)
- 対談 「法学教育」をひらく (17)
- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)
- 年度まとめ (10)
- 往復書簡 (10)
- 河村先生から荒木先生へ (5)
- 荒木先生から河村先生へ (5)
- 教科書を見るシリーズ (21)
- 法教育素材シリーズ (7)
