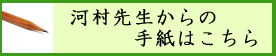高校教諭と労働法学者の往復書簡(3) 「労働法と経済」
河村先生からのお手紙に対する荒木先生の返信です。
(右上の文字サイズを「中」にしてご覧ください)
6月は国民の祝日のない月ですが、梅雨で天候にも恵まれずに生徒も教師もなかなか辛い季節ですね。お元気でいらっしゃいますか。
さて、今回は「勤労基準の法定」、すなわち労働条件の最低基準を法律が定めることについて考えようというテーマでした。河村先生は、この問題に「経済から見た労働法と労働法から見た経済」という視角から迫ってみようという指導案を提示されました。労働法による労働条件規制の意味を「経済」「市場」という補助線を引いて明らかにしようという構想のように受け止めました。先生の問いかけは、「市場調整(市場機能)」と「法規制」という財の配分、人間の行動、ひいては社会のありようをコントロールする2つのメカニズムをどのように考えるのかという根源的な問題に連なるものです。いつもながら、物事の本質まで遡って考えさせようとされる河村先生の真摯な姿勢がひしひしと伝わって参ります。このような根源的な問いは、何が正解かというより、正解を求めて考えることに大きな意味があるように思います。学生達から、しばしば正解のわからない問いを投げかけられることがあります。そういうときは、「何が正解か、私もわかりませんので、一緒に考えてみましょう」と、ともかく学生と一緒に藻掻いてみることにしています。今回も、答えにたどり着けるかどうかわかりませんが、藻掻いてみることにしましょう。
■ なぜ最長労働時間規制や最低賃金規制が必要なのか
当為からの出発・事実からの出発
なぜ労働条件の最低基準を法律で規制する必要があるのか。指導案は労働基準法1条1項の「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」というまさに当為を読ませて、最低労働条件規制がなぜ必要かという問いかけに進むようです。当為を法が宣言し、そのために法規制が定められているとすれば、正しいアプローチといえましょう。ただ、何が当為なのかは、人によって議論が分かれうるところです。誰もが否定しないように思える労働基準法1条1項の命題についても、例えば、人たるに値する生活を保障すべきは国家の社会保障制度であって、それを個々の企業・使用者の設定する労働条件で確保すべきと考えるのはおかしい、という議論も一部にあります。
法規制は、社会実態の中で、人々が法規制の必要を実感し、それが立法プロセスを経て立法に結実していくということが多いようです。労働法の歴史はまさにそうだったように思います。そうすると、最長労働時間や最低賃金について、何らの規制がない中で、過去に労働者がどのような状況に置かれることになったのかという事実から出発し(政治・経済の教科書等に掲載されている産業革命初期に女性・児童が酷使されている挿絵等を示してもよいでしょう)、そうした歴史的経験から法規制が導入されていったことを認識させるというアプローチもあるように思います。
最低労働条件基準の設定=契約自由原則の修正
ところで、最長労働時間や最低賃金という最低労働条件を法律で定めたということは、労働条件は契約で自由に合意して設定してよい(労働者も使用者も対等な市民同士なのだから合意したとおりの契約を守るべき)、という民法の契約自由の原則を修正したということです。この労働法の最も重要な意義を認識させるためには、労働基準法13条の規定を読ませることが非常に大切だと思います。
労基法13条は「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と定めています(最低賃金法では同旨の規定が4条2項にあります)。つまり、労働者が合意した労働条件であっても、それが労基法・最賃法の定める基準に達しない場合には無効となり、労働者はその約束に拘束されません。広島県では、労働者が時給650円でいいですと使用者と約束しても、最低賃金719円の基準に達しない労働条件ですので、そのような約束(契約)は無効で、労働者は719円の時給を請求できることになります。
入社時にこの労働条件でいいと約束したから、自分は労働法の保護を受けられなくても仕方がない、と思っている労働者が少なくありません(民法の世界、契約自由の考え方の下ではそう考えても不思議ではありません)。しかし、労働者と使用者という交渉力に格差のある当事者間で、約束した以上は守るべきだ、という契約自由の原則を維持することは、かえって正義に反するとの考え方が広がり、労働法は民法の原則を労働者保護のために修正することとしたわけです。
教材プリントⅠ(2)では「民法では(労働者)の保護が十分ではないので、労働法を制定した」という命題を認識させることになっています。生徒の中には、この命題を、民法にも労働者保護の規定があるけれども、その保護の程度が不十分なので労働法ができたのだ、と理解(誤解?)する者もいるかもしれません。大切なことは、労働法が登場したのは保護の程度が不十分だから、という問題ではなく、契約条件(労働条件)は自由に合意で決めてよく、決めたらその通り守らなければ契約違反の責任(損害賠償等)を負わされる、という契約自由の考え方自体を変える必要があったからなのです。このことを生徒達にきちんと伝えるには、労働基準法13条を読ませるのがよいでしょう。
念のためと、高校生の娘の政治・経済の教科書を借りて巻末資料を見たところ、その教科書では、労働基準法抄録には残念ながら労基法13条が省略されて掲載されていませんでした。初回に触れた「労働法を知る」という観点(最低基準が1日8時間、週40時間と認識する等)からは、具体的な労働条件基準に触れた条文ではないので省略可とされたのかもしれません。しかし、「労働法で考える」視点、すなわち、労働法の視点から社会の法現象を捉え理解するという法教育の視点からは、労基法13条は省略せずに掲げる価値があるように思います。
■ 最低労働条件を規制することに問題はないのか(その1)
今回の教材では、労働条件規制のデメリットの問題が市場調整への法介入の是非として提起されていますが、その前に憲法との関係について、一言触れておかれてもよいかもしれません。
すなわち、資本主義社会においては、契約の自由が大前提とされ、憲法上も(営業の自由を含む)職業選択の自由(憲法22条)や、財産権の保障(憲法29条)によって保障されていると解されています。したがって、国が、法律で最長労働時間や最低賃金を規制することは、憲法違反ではないかという重大な問題を惹起します。実際に、アメリカでは、19世紀から20世紀初頭にかけて労働時間規制立法、最低賃金立法が裁判所で契約自由を侵害するものとして違憲判決が下され、労働立法の大きな障害となりました。憲法27条2項が「勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定していることは、政府に労働条件を規制する法律制定の政治的責務を課すと共に、契約自由を制限する労働条件規制立法が憲法に基づくもので合憲であることの重要な根拠を提供していることになります(文献等を含め荒木尚志『労働法(第2版)』23頁(有斐閣、2013年)参照)。
■ 最低労働条件を規制することに問題はないのか(その2)
さて、今回の本題は、労働条件の最低基準を法律で規制することが、市場による調整機能を阻害し、結果として労働者にとっても望ましくない事態を引き起こすことにならないのか、という問題です。
労働市場で仕事を求める人が増加すると、労働力の供給曲線は右に移動する結果、需要曲線との交点である価格はどんどんと下がってしまいます。私は、アメリカの著名な労働法の大家から次のような話を聞いたことがあります。彼は、1929年の大恐慌の後、工場の門の前で、その日の仕事を求める大量の失業者と工場側のやり取りを目撃したそうです。工場側の求人は数人、その仕事を求める失業者は100人以上という中で、失業者のある1人が自分は所定の時給より低くてもいいから雇ってくれ、と言うと、別の失業者は、自分は彼の言う時給よりもっと安い時給でよい、と言いだし、失業者の間で賃金切り下げ競争が展開されたといいます。そして、最後には失業者同士の喧嘩になってしまったそうです。労働市場に法が介入せずに需要と供給の市場調整に委ねた場合の1つの典型的な帰結です。
このエピソードに対しては、市場に失業者があふれていた時代はそんなこと(労働市場が独占的状態にあるいわゆる「市場の失敗」)があるかもしれないけれど、少子化時代で労働力が不足するといわれている現代でも同じようなことになるのか、あるいは、市場による調整に法規制で枠をはめると、企業は安い賃金で雇えないのなら労働者を雇うこと自体をやめることになり、結果として失業者が増えることにならないか、という疑問が提起されるかもしれません。
しかし、最低賃金規制には、賃金という労働力の価格決定メカニズムを労働者保護の観点からのみ規制しているのではありません。最賃法1条は最低賃金規制の目的として、「公正な競争の確保」や「国民経済の健全な発展」に寄与することも挙げています。公正競争の確保は、先の例では、こんなに困っている労働者達に時給の「競り」をさせるようなことで賃金を引き下げて雇うのは正しくないと考える別の企業が、通常通りの時給で雇用したとしましょう。しかし、賃金を買い叩いた企業は安い労賃で製造した商品を安い価格で市場に出すことができ、通常通りの時給で雇用した労働者思いの企業の製品は価格競争に負けてしまいます。こうした賃金切り下げ競争を放任せずに「公正な競争を確保」しようとする意図が最低賃金規制には含まれています。
そして、近時、アベノミクスにおいても議論されているように、国民経済の発展には労働者の購買力を確保することが必要とすれば、その観点からも賃金切り下げ競争には一定の枠をはめる必要が出てきます。
しかし、経営者側からは、貨幣価値が10分の1といったアジアの新興国と国境を越えて競争しなければならないのに、日本の国内だけで最低賃金規制などしてもらっても困る、賃下げができないなら、国内の工場は畳んで、アジアに移転させざるをえず(産業空洞化)、結局、日本の雇用が失われ失業を増やすことになる、といった主張も出てくるかもしれません。前者は法規制が国家の枠内でなされているのに競争や経済はグローバル化しているという問題、後者は、低価格でしか新興国と競争できない産業は、低賃金を許容して延命させるのではなく、むしろ産業転換を図るべきではないかという反論も含めた検討が必要な問題です。
このように考えてくると、問題は非常に複雑でかつ錯綜しているようです。そして、「市場の失敗」に対処するために法規制が必要だとしても、その規制内容については、価格を直接規制するような労働条件規制ではなく、「市場の失敗」が生ずる独占・寡占状態を解消するような規制(独占禁止法による規制等)こそが試みられるべきだ、使用者の買手市場状態が労働者(求職者)の交渉力を低下させているのなら、労働者が別の転職先をスムーズに探せる仕組みを整えることで対処すべきだ等、様々な議論がありそうです。
■ 労働者が多様化する中での労働条件規制
最低賃金規制を中心に見てきましたが、労働時間規制については、さらに難しい問題があります。最低賃金規制については、より低い賃金で働きたいという労働者はあまりいないと思いますが、最長労働時間規制については、法定労働時間以上働きたいという労働者がいてもおかしくありません。労働基準法は、1日8時間を超える労働(法定時間外労働)に、2割5分増しの割増賃金支払いを義務づけています(労働基準法37条1項、割増賃金令)。そうすると、多くの賃金を得るために、より多くの時間外労働をしたいという労働者もいるかもしれません(住宅ローンを抱えている労働者にとっては切実な問題です)。また、4月のお便りで触れたようなiPS細胞の研究者は、労働時間の規制から自由に働きたいと考えるかもしれません。
長時間労働に苦しんだ労働者を救うために最長労働時間規制が導入されましたが、ある労働者にとっては必要な保護規制が、別の労働者にとって必ずしも保護にはならず、むしろ自ら選択した働き方を阻害しているのではないかという問題です。かつて労働者が等しく交渉力が弱く、志向も均質であった時代には妥当であった一律的規制が、今日のように様々な能力・志向・家族事情を持った多様な労働者については、必ずしも適切でない可能性があります。
しかし、本人が働きたいというのなら働かせればよいか、というとこれも簡単ではありません。ワーカホリック(仕事中毒)という言葉がありますが、労働者自身、長時間労働の歯止めがきかなくなっていて、体調を崩したりうつ病になってしまうまで働いてしまうことがあります。そうすると、本人が働きたいと言っても、やはり健康確保のための規制は必要ではないか。また、労働需要が増大しても、既存の労働者に長時間労働させる方が採用・訓練コストがかかる新規採用より企業にとって安上がりであれば、折角の景気回復も失業問題・若年雇用問題の改善につながりません。そうすると、労働市場政策の観点からも長時間労働を規制する必要があるのではないか。さらには、健康問題・労働市場問題を別にしても、ワーク・ライフ・バランス(職業生活と私生活の調和)という観点からの労働時間規制も必要ではないか。
このように、歴史的に労働者保護のために必要と考えられて導入された労働条件規制も、経済状況・労働者像の変化によって、再検討の必要性が認識される一方、その規制が不要かというと、なお別の、現代的観点からの必要性も主張されているという状況のようです。換言すれば、労働条件保護というシンプルな目的を担っていた労働法の労働条件規制は、複雑化多様化する社会のニーズに対応して、多様な任務を引き受ける規制へとその内容を発展させてきているようです。
■ 経済学と法律学のコラボレーション
さて、「経済から見た労働法、労働法から見た経済の違い」に関する先生の最後の問いは「経済は法則、法学は当為」なのか、というものです。確かに、経済学者と法学者の議論は、かみ合わないことが少なくありません。経済学者は大多数の原則的傾向を論じ、法学者は裁判となった極めて例外的事象に着目して議論する傾向があるなど、学問の性格を反映した違いもあるのかもしれません。
しかし、最近では、「法と経済(Law and Economics)」という法律学と経済学の融合的研究が発展しつつあります。労働の分野でも法学と経済学のコラボレーションの模索が始まっています(例えば、雇用問題について法律学と経済学の両方の視点から検討したものとして、荒木尚志・大内伸哉・大竹文雄・神林龍編『雇用社会の法と経済』(有斐閣、2008年)、神林龍編『解雇規制の法と経済』(日本評論社、2008年)、大内伸哉・川口大司『法と経済で読みとく雇用の世界』(有斐閣、2012年)等)。
法規制も市場による調整メカニズムも、いずれも人間社会のありようを規定する仕組みです。先生がおっしゃるように、法規制は立法者が選択した1つの当為を反映した制度ということもできます。しかし、当該法規制が実際にいかなる効果をもたらすかを度外視して、規制を議論することはできません。また、ある目的を達するためには、法規制による他に、一定のインセンティブを与えて人々の行動を誘導するといった手法もありえます(ハードローに対するソフトロー)。これらの場面で、経済学の知見は非常に示唆に富みます。
他方、経済学においても、市場は万能なのではなく、市場の失敗がありえ、その場合には法規制が正当化されると論じられているようです。その際にどのような法規制を導入するかは、法規制の技術的な面を含めて法学とのコラボレーションが不可欠です。また、市場と規制は常に対立するものではなく、市場機能を発揮させるために規制が活用される場面もあります。例えば、CSR(Corporate Social Responsibility企業の社会的責任)に関して、社会的責任を果たしている企業により多くの資本が投下されるようにするためには、CSRに関する企業の情報を開示させることが必要です。そうした情報が開示されればSRI(Socially Responsible Investment社会的責任投資)が機能します。ここでの法の役割は、CSR自体を企業に義務づけることではなく、SRIにおいて市場が機能するように、情報開示を義務づけることです。そのほか、法規制は社会の制度を形成し、経済や市場メカニズムもその制度の下で展開するものですので、制度の正確な理解を欠いた市場機能分析というものも成り立ちません。
お手紙を書きながらあれこれ考えてきましたが、労働法が経済を窒息させるものであっては労働法の目指した目的も達成できず、他方、経済は労働法の取り上げようとした社会問題を無視しては持続的発展が望めないもののようです。そして、そのことを認識するためにも、法学と経済学はまさに補完的に協働すべき社会科学といえるのではないかという気がして参りました。答えがでるか不安なままに藻掻いてみましたが、果たしてお答えになっているか、まったく自信がありません。しかし、またしても長いお手紙となりましたので、私も頂いた課題を考え続けることとし、今回はこの辺りで失礼します。
アーカイブ
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
カテゴリータイトル
- インタビュー (16)
- はじめに (1)
- 取材日記 (325)
- 報道から (5)
- 対談 「法学教育」をひらく (17)
- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)
- 年度まとめ (10)
- 往復書簡 (10)
- 河村先生から荒木先生へ (5)
- 荒木先生から河村先生へ (5)
- 教科書を見るシリーズ (21)
- 法教育素材シリーズ (7)