「法学教育」をひらく(第2回) 青木人志先生 その2
〈本から離れて―法学の魅力とは〉
大村:「本そのものから少し離れますが、法学の意義、面白さということについては、ご自身の個人的な経験も含めていかがですか? 「法学入門」とは別になさっているご自身の研究・教育について、法学の魅力と絡めて、お話し願います。」
青木:「自分自身の研究と法学の面白さという2つのことは、幸い私の中でかなりつながっています。私は動物法を研究していますが、きっかけは偶然です。大学院生時代に、「フランス刑法研究会」という研究会に参加したのですが、その研究会は國學院大學法学部の紀要の紙面を借りてフランス文献の翻訳紹介を続けていました。フランスはちょうど生命倫理法に関する議論が盛んだった時期で、私はフランスの動物実験についての法規制の紹介を研究会内部で割り当てられました。それまでそんな問題を考えてみたこともなかったのです。そして、その文献を読んで、ヨーロッパ人は動物のことをなんて熱心に論じているんだろう、と驚きました。まさにこれは、比較法文化論の好素材です。当時日本には、そもそも動物法に関して議論した法学者がほとんどいなかったですね。そんなわけで動物法に関する比較法文化論の論文をいくつか書いたら、たちまち第一人者扱いになりまして、途端に社会とのつながりができ、研修会や講演会などに頻繁に呼ばれるようになりました。この問題に関心をもっている人が社会にたくさんいたのです。動物保護団体の方はもちろん、動物行政の現場で苦慮している役所の人もいたし、獣医さんなどの動物関係者の中にも内外の法制度を知りたがっている人はいました。そんなわけで、動物法研究者として、急に大学外のいろいろなところに呼ばれるようになり、自分自身が、自分と社会と法という三者の関係を問われるところへ、否応なく置かれることになりました。
そういった場に出てゆくと、非常に頻繁に「なぜ法律では動物はモノなのか?」という問いを投げかけられるのです。最初のうちは、そのような問いは「どうしようもなく素人的な問い」だと思いましたが、次第に考えが変わりました。そして今では、このように社会の中から沸き起こってくる「動物はモノとは思えない」という率直で骨太の主張を玄人の法学者が法学の世界につないでいくべきではないかと思うようになりました。「法学は未来へ向かって開かれている」と学生に教えている立場なんですから。現在は法の世界は「人」と「物」という2つの礎石の上に構築されていますが、もしかしたら将来、法の世界が「人」と「物」と「動物」という3つのカテゴリーで構成されるかもしれない。そういう一種の躍動感を自分でも感じるようになりました。法学って面白いと学生たちの前で自信をもっていえるようになったのは、動物の問題に関わってからです。だから私の場合は、自分自身の研究テーマがまさに法学の魅力を体現しているという実感があります。」
〈動物法について〉
大村:「私も2005年の小著に動物法のことを少し書いてみましたが、中学生などにも反響があります。この間も、動物法人論はその後はどうなりましたか、と質問されました。動物法人論というのは、動物にも、人間と同じように、権利の主体としての地位(法人格)を認めたらどうか、という議論ですね。」
青木:「アメリカのアニマル・ライツの論客であるフランショーン(Francione)という法学者が、『人としての動物』(Animals as Persons)という本を書いています。一橋大学の教養ゼミで現在その本を学生諸君と一緒に読んでいますが、若者の間でかなり関心の高い議論で、10名を超える諸君が参加してくれています。」
大村:「民法総則の教科書に法人が出てきます。日本法では社団法人と財団法人が対等 な形で定められていますが、歴史的にはまず社団法人が認められ、その後に財団法人が出てきます。財団法人というのは脆弱なもので、国によっては、いまでも十分に認められていなません。歴史的文脈の中で見ると、法人格に対する考え方がどういう要請で変化してきたかがわかります。動物もそういう流れで位置づけると、法人論としても面白いと感じました。」
青木:「教育的な思考実験としても面白いと思います。民法は、相続人がいないとき、相続財産は法人になると規定しています。もし「財産」が法人になることができるなら、温かい血が通って感情も知恵もある「動物」なら、なおさら法人になれるのではないか?ただし、仮に動物の一部を法人と認めるとしたら、そのことによっていったい法律上「何が」可能になり、そして、その反面、どのような副次的効果を甘受する必要があるのか?そういう問いを学生たちに投げかけています。」
 大村:「『日本の動物法』は、そういう問いに対するポジションをどう考えていますか? 動物関係に限りませんが、判例には現れないけれど、どうするかを誰かが決めねばならない問題というのがある。それをどうするかが法学的には面白いと思います。さらに、法律家だけの問題でなく、役所や一般の人が関わる議論、職際的といえばいいのかと思いますが、そういう議論のための法学が必要だと思います。」
大村:「『日本の動物法』は、そういう問いに対するポジションをどう考えていますか? 動物関係に限りませんが、判例には現れないけれど、どうするかを誰かが決めねばならない問題というのがある。それをどうするかが法学的には面白いと思います。さらに、法律家だけの問題でなく、役所や一般の人が関わる議論、職際的といえばいいのかと思いますが、そういう議論のための法学が必要だと思います。」
青木:「出身校であり勤務先でもある一橋大学は自由なところで、恩師は刑法の先生ですが私を自由放任にしてくれました。担当している「比較法文化論」という授業も自由な素材を使えるので、教室でも「どうしたら引き取られた犬猫の殺処分を法というツールを使って減らすことができるのか」といった問題を、いわば立法政策論として考えさせることがあります。学生たちは生き生きと議論します。そのほかにも、たとえば犬による咬傷事故を減らすため、英国には危険犬種に着目した細かい法規制がありますが、日本にはない。英国と日本、両方比べてその利害得失は何か、日本において英国と同じような法を作るべきなのか、といったことを考えさせるのです。」
〈専門家と非専門家の間の往復・架橋〉
大村:「社会工学というものがありますが、政策形成に関与している人・法律専門家にならない人にとって、法学を社会を変更していく学問としてとらえることが重要だと思います。1980年代の「法政策学」にはそういう面がありましたが、こうした考え方に親近感をおもちですか?」
青木:「ロースクールを出てから政策や法律の専門家にならない人がいても、それはそれでいいのだ、と思います。穂積重遠先生の「法律家を非法律家に、非法律家を法律家に」という言葉には、感銘を受けました。法学を法律専門家でない人のものにするという機能を、私も果たしたいと思います。市民が法を自分にとって身近なツールとして実感できるようにする、ということです。そのため私は、高校への出張講義やオープンキャンパスも進んで引き受けています。」
大村:「私自身も民事司法の専門家ではないという意味で、法律家ではあるけれど固有の意味での専門家ではありません。先生は、司法の世界と様々な分野の専門家がいて、それらの専門家と非専門家をつなぐポジションを積極的にお引き受けになろうとしていると思います。」
青木:「はい、私もその役割を引き受けたいと思います。とくに法学入門の講義は自分の性に合っており、自分の得意なことでもあると思うので、今後も力を入れてやりたいと思います。高度の専門性という評価基準からすれば、法学入門に熟達しても「学者」としての評価には結びつきませんが、私自身の「教師」としてのアイデンティティと自負という観点からは、法学入門はかなり重要な地位を占めます。」
大村:「法学入門は専門家がいない、専門の世界でないということは、法学入門は何かと何かを「架橋」しているのだと思います。法学入門を教えるとは、どこでもないポジションに立って、何かと何かをつなぐことという気がしてきます。入門を教えた経験から、法学者へ何かをフィードバックできるとすると、そういうところに立っているということが教育上もっている力、役割を示すということがあるのではないか。実定法学も実は境界に立っているのだから、それを十分に使って教育することができるのではないかということ、そうした指向性というか可能性かいうか、それを法学入門の側から伝えることはできるのではないかと思います。」
青木:「そういう議論をすることは重要かもしれませんね。オープンキャンパスを積極的に開催したり、高校までの法教育を大学の側にいた法学教師が真剣に考えたりし始めたのは、ここ10数年くらいの新しい現象です。法学者が、社会や素人とのつながりをもっと考えることが、今後は必要だと思います。」
〈法学入門の教科書について〉
大村:「何か、話し残されたことはありませんか?」
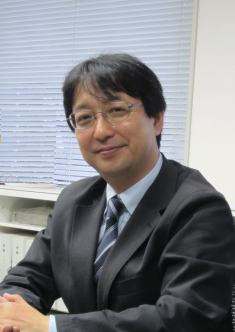 青木:「学生に対して「情熱的に語りたい」という思いが自分にはあります。それは多分、私自身、情熱的な語り口の法学論文に感銘を受けた経験があることと関係しています。たとえば大学院生時代に読んだ2つの論文はいまでも忘れられません。一つ目は、米倉明先生の「積極的破綻主義でなぜいけないか―有責配偶者の離婚請求についての一試論」という論文(ジュリスト893号)です。論理を展開してゆく米倉先生の語り口に「法学ってこんなに情熱的な学問なんだ!」という新鮮な感銘を覚えました。もう一つは野田良之先生の「サレイユにおける自然法の客観的実現」という戦時中に発表された長い論文(のちに『法における歴史と理念』東京大学出版部1951年に収録)です。かなり難解な論文ではありますが、戦争という厳しい環境の中で、若き東大助教授であった野田先生が、万物が流転する中に確実不変なものがはたしてあるのか、という哲学・法学の大問題と、真正面から格闘しているのです。そのような書き手の情熱がひしひしと伝わってくる論文は、当時、年若い読者だった私に強く訴えかけました。そういうケレン味のある書き方は嫌だという先生もいますが、若者に向けては、あえてケレン味のある言い方も辞さない態度が法学入門担当者にあっていいと思います。
青木:「学生に対して「情熱的に語りたい」という思いが自分にはあります。それは多分、私自身、情熱的な語り口の法学論文に感銘を受けた経験があることと関係しています。たとえば大学院生時代に読んだ2つの論文はいまでも忘れられません。一つ目は、米倉明先生の「積極的破綻主義でなぜいけないか―有責配偶者の離婚請求についての一試論」という論文(ジュリスト893号)です。論理を展開してゆく米倉先生の語り口に「法学ってこんなに情熱的な学問なんだ!」という新鮮な感銘を覚えました。もう一つは野田良之先生の「サレイユにおける自然法の客観的実現」という戦時中に発表された長い論文(のちに『法における歴史と理念』東京大学出版部1951年に収録)です。かなり難解な論文ではありますが、戦争という厳しい環境の中で、若き東大助教授であった野田先生が、万物が流転する中に確実不変なものがはたしてあるのか、という哲学・法学の大問題と、真正面から格闘しているのです。そのような書き手の情熱がひしひしと伝わってくる論文は、当時、年若い読者だった私に強く訴えかけました。そういうケレン味のある書き方は嫌だという先生もいますが、若者に向けては、あえてケレン味のある言い方も辞さない態度が法学入門担当者にあっていいと思います。
それから別の観点ですが、教科書の大事な性質として、「書き過ぎない」ということがあると思います。全て書いてあったら、教科書を読むだけでいいわけで、講義の意味が半減します。良い教科書の満たすべき条件の一つに、情報量が多過ぎないことというのがあると思います。教科書はせいぜい幹と太枝、講義は葉と細枝を補うもので、講義に出ることによってそれが一つになって教科書に素描された樹木全体の姿が生き生きと眼の前で動き出す、そういう講義が良い講義です。つまり、講義者とセットになって初めて、良い教科書ということが確定すると思います。ただし、いま述べましたように教科書で幹や太枝を記述する際にも、肉声で情熱的に語ることは重要だと思います。教科書は面白く読めるに越したことがない。「読める」(readable)であることは重要です。『グラフィック法学入門』については、ある学生が、「青木先生の教科書は、読み物として普通に面白い。」という感想をツイッターで述べていることを、別の学生がみつけて教えてくれました。そういう側面も教科書として重要なことだと思っていますので、とてもうれしい感想でした。」
大村:「先ほど言及された穂積重遠は、講義というのは、教師と学生とが共同で教科書に注をつける作業だ、というようなことを言っています。また、日本の「読める」教科書の始まりも、穂積や末弘厳太郎あたりだろうと思います。青木先生はその系譜に連なるということになる。」
〈高校の先生方に向けてのメッセージ〉
大村:「高校で法を教える先生方に向けてのメッセージはありますか?」
青木:「「法学を学ぶ上で必要な基本知識」は、早めに教えていただきたいと思います。問題は何がそれにあたるか、ということです。私の単なる印象かもしれませんが、高校までの社会の授業で憲法上の制度や、人権に関係する憲法訴訟のことはかなり詳しく教えらえています。しかし、たとえば処分権主義のような民事訴訟の基本原理は教えられていないのではないでしょうか。実際、法学部新入生は、しばしば裁判所を「遠山の金さん」みたいなイメージでとらえ、無用な誤解をしています。ごく基本的な枠組みでいいから、刑事手続と民事手続、とくに後者の概略を教えておいてくださると、あとあと知識の肉付けがしやすくなると思います。
さらに、憲法訴訟のような大上段の問題ではなく、もっとずっと日常的なものから法にアプローチする教育があっていいと思います。法学部に入ってくる学生は、法=裁判と思い込んでいて、訴訟を十重二十重に取り巻くさまざまなADR(Alternative Dispute Resolutions裁判外紛争処理)や、当事者が納得すれば裁判を起こさなくていいのだということを、意外と認識していません。かくいう私も、民法を最初に勉強し始めたときは、私的自治がよくわからなかったし(笑)、契約が裁判において法律と同じ効力をもつということも、よくわかっていませんでした。「上から降ってくるような強行規定」ばかりが法であるという間違ったイメージを与えない教育が、もっとあっていいのではないか。裁判は、たしかに法システムの中心・核心にあるものですが、法という広大な世界の一部にすぎないということや、民事法の世界には私的自治という広大な領域があることが最初から十分にイメージできている学生はあんがい少ないので、高校までの教育でも、そういった点にも気を配ってもらいたいと思います。」
大村:「訴訟の意義ということは、明治初期の日本人法律家にもわかりにくいことがあったと思います。たとえば、フランス法では書証の大事さが裁判の前提になっています。裁判所は万能ではない、しかし、書証があれば何とかしてくれるところだ、という感覚をつかむことが難しかった。お話を伺いながら、そんなことを考えました。」
青木:「最高裁判所は正義の最終体現者だと理解されているところがあります。その辺のイメージも問題で、「法がすなわち全人間的正義を汲み上げる」ということは、現実にはありえません。法にはその性質からして多くの限界があり、それ以外の社会統合システムを全部含めて、人間としての正義を担保するトータルな社会システムを、私たちはつくらねばならないのだという感覚を、早めに養っていただければいいと思います。こういう一般的な、抽象的な言い方ですと、高校までの先生方は何をやればいいかわからないとおっしゃるでしょうが、まさにそのために何をどう教えるかを、大学教員と小・中・高の教員の共同作業として今後考えてゆくべきことなのだとおもいます。」
大村:「ありがとうございました。」
グラフィック法学入門 |
||
 |
著 者 判 型 頁 数 発行年月 定 価 発 行 |
青木人志 著 A5判 197頁 2012年8月 1,800円(税抜き) 新世社 |
アーカイブ
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
カテゴリータイトル
- インタビュー (16)
- はじめに (1)
- 取材日記 (325)
- 報道から (5)
- 対談 「法学教育」をひらく (17)
- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)
- 年度まとめ (10)
- 往復書簡 (10)
- 河村先生から荒木先生へ (5)
- 荒木先生から河村先生へ (5)
- 教科書を見るシリーズ (21)
- 法教育素材シリーズ (7)
