「法学教育」をひらく(第5回) 西原博史先生・仲道祐樹先生 その1
〈著書と著者のご紹介〉
大村:「西原博史先生は早稲田大学社会科学部教授で、憲法をご専門にしておられます。著書には『良心の自由』(成文堂 1995年、増補2001年)、『平等取扱の権利』(成文堂 2003年)、『良心の自由と子どもたち』(岩波新書 2006年)などがおありです。今回は『うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う』(太郎次郎社エディタス 2014年)に関するお話を伺います。
仲道祐樹先生は早稲田大学社会科学部准教授、刑法がご専門です。著書に『行為概念の再定位』(成文堂 2013年)がおありです。『おさるのトーマス、刑法を知る』(太郎次郎社エディタス 2014年)は、『うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う』とともに「なるほどパワーの法律講座」シリーズを形成しています。
『うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う』『おさるのトーマス、刑法を知る』は読者に小学生を想定している点で他に例を見ないものになっています。この2冊は独立に書かれたのではなく、シリーズとして明確なコンセプトに基づいて書かれました。内容はかなり高度で、異色の法学入門として大学生が読んでも得ることが多いものになっていると位置づけられると思います。」
〈本書執筆の発端について〉

西原:「子どもゼミは人形劇で物語を紹介しながら展開しますが、人形劇のシナリオが溜まるうちに、1回限りで消えるのはもったいないと思い、単行本化を考え始めました。教材集というよりは、メッセージを伝えるものにしたいと考え、イメージをすり合わせることができた太郎次郎社エディタスにお願いすることになりました。」
仲道:「子どもゼミは2012年度に行い、本の制作はゼミ終了前後の2013年になりました。」
大村:「最初に子どもゼミをやろうと言われたのはどなたですか?」
西原:「江戸川区子ども未来館の松井朋子さんからの依頼によります。松井さんは法学部の出身だそうです。子ども未来館のゼミは、従来、理科系が中心で、社会科学系のトピックがほとんど扱われてきておらず、扱うノウハウもない。経済のゼミは始まったけれど体系的なものが伝わりにくい感があり、法学ではどうだろうかとのことでした。『良心の自由と子どもたち』で、自分で考えることのできる子どもを育てられるはず、と書いた手前、引き受けざるをえないことになりました。かといって、1年間12回の講座を担当するには、自分一人では手に余りそうなので、刑法の仲道先生に助けを求め、1年の半分を受け持ってもらうことにしました。」
仲道:「お話が来たのは2011年の10月頃でした。ちょうど専任教員としての2年目で、学位論文を書き終えて、大学で授業をすることにも慣れ始めた頃でした。FD関係のワークショップで報告する機会もあり(その内容については『大学時報』356を参照)、法律学の教え方について自分なりに考え始めた時期でしたので、それが小学生相手に通じるか試してみたいという気持ちもあって引き受けました。」
西原:「仲道先生の学生への語りかけに対する評価は高いし、刑法は子どもたちになじみがあると思い、頼みました。」
〈本のコンセプトやフォーマットに関して〉
大村:「子どもゼミをサルなどの動物が主人公となる人形劇をもとにして展開するという方式は、その時点ですでにお考えでしたか?」
仲道:「ある日、唐突にシナリオがメールで送られてきました。」(笑)
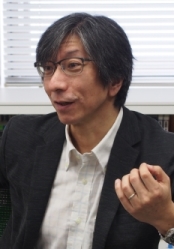
仲道:「シナリオがメールで来る前は、別のやり方を考えていました。ドラマのように、家族が逮捕されたら? という話題から始めて、刑罰とは何かについて話そうか、とかです。ただ、人間、特に身近な大人を例にあげると、どうしても生々しい話になってしまいます。そこへ「サル山共和国」のシナリオが来ましたので、サル山共和国という設定によって生々しさ、血生臭さが緩和できると思い、賛同しました。西原先生と、どういう舞台設定がありうるか相談しながら、具体的な設定をしました。宿題忘れの罰掃除よりも、廊下でかけっこをして友だちを怪我させるなど加害性がある方がいいかなどです。その中で、学校の中の違反行為と刑事事件を重ね合わせるフレームになっていきました。この事件はこう解決されるということにせず、解釈が分かれるところへフォーカスし、解釈が説得力を持つかどうかを重視することにしました。
刑罰の正当化根拠論の次に共犯が来る授業構成は、刑法の講義のセオリーを外れる、アクロバットなものです。ただ、子どもゼミで、廊下を走って他人にケガをさせた場合、周りではやし立てた子どもも悪いという意見が強く出ました。子どもにとって、どこまで一緒にやるのが悪いことなのか、いいことなのかを考えることが大事だと感じたので、法学教育の常識にとらわれないことにしました。」
大村:「2012年度の子どもゼミは自転車操業で、お2人とも走りながら考えていたんですね。」(笑)
仲道:「基本的な世界観を受け継ぎますというレベルで、サル山共和国シリーズのコンセプトが共有されました。」
大村:「人間の世界ではないので、ドロドロしていないが、学校が舞台なので子どもにとっては身近に感じる。解決を与えるよりも、どういう解決があるか考えるについて、説得力を重視するということですね。」
西原:「教え込みではないことは、早くから2人の間で共有されていました。」
〈コンセプトの深化や子どもたちの反応の摂取〉
大村:「基本コンセプトがだんだんと煮詰まっていくということはありましたか?」
西原:「ゼミの子どもに戸惑いが見えると、松井さんがコンセプトを確認したいと言って、3人で打ち合わせをしました。その場で、こういうふうにしたいんだと、将来展望を作っていったのです。」
仲道:「2~3か月に1回は、この先のユニットをどうするか、打ち合わせました。」
西原:「年間スケジュールが組まれたのは、秋口になってからです。」
仲道:「もともとは、夏休みに裁判傍聴をする予定だったのですが、小学生以下は裁判傍聴できないとのことでした。その代替案として、模擬裁判を実施することに決めたのが夏でした。」
大村:「ゼミをして、子どもの反応を見ながら内容を考えるということはありましたか?」
西原:「第1回目は憲法で、とても厄介なケースだと思いますが、子どもたちの食いつきはかなりよかったです。法律論として論争のありうるポイントに、子どもたちも、きちんと食いついてくれました。ディスカッション・リーダーの果たした役割も大きかったし、子どもたちも楽しんでくれました。ゼミの後に、憲法ってこんなに面白いとは思わなかったと言いに来てくれた女の子がいて、嬉しく思いました。素材を与えて、組み立てるやり方で間違っていないと感じました。基本的に結論は出さないというやり方でよいのだ、という安心感が得られていきました。」
〈本として整理する段階について〉

西原:「そうです。最初に仲道先生と、筆者の思いを読者に押し付けないという方針だけは決めていました。問題の解決方法は複数ある。論点は拡散していいし、いくつか挙げてほしい。考え続けたい思いをもって1つのチャプターを読み終わってほしい。きれいにまとめずに終わらせるためには、どうすればいいかと考えていました。語り手の思いに集約してしまうことを回避するには、どうすればいいかということですね。」
大村:「子どもゼミのすべてが活字になるわけではないので、授業後に本にするために整理をしますね。その段階では何を相談されましたか?」
西原:「太郎次郎社エディタスの社長からは、子どもは飽きたら本を閉じる。自分が今何をしているのかわからなくなる瞬間が来たら、本を閉じると言われました。本の著者に考えてと言われても、何をやるかイメージできない恐れがあるということでした。ゼミでは「考えよう」で済んでも、本では解説という責任を引き受けねばなりません。「ここは共有しよう」ということは解説しなければなりませんでした。」
大村:「授業ではオープンクエスチョンで終わったところを、本ではまとまりがついていないと、小さな読者には厳しいということですね。」
仲道:「本は1人で読むものなので、読み通せることと、次を読みたいと思わせることが必要でした。読み通す手助けとして引っ張る役割を解説が担うということでした。」
大村:「書き手としては、物語から一歩ひいて、「物語はこうだけれど」と解説する方が 書きやすいですね。私もこのシリーズ3冊目を書くときに、子どもは「この先どうなるの?」と思うから、ともかく物語の結末を示しておいてくれないと、と出版社から言われました。仲道先生は、学術論文との落差が大きいと感じられませんでしたか?」
仲道:「解説が一番苦労しました。児童小説家のような気持ちで学術的な文章を書くのはこれまでにない経験でした。一方で、自説の押しつけや、正解の提示と受け取られるような説明はしたくない、というコンセプトもあり、ここはかなり考えました。刑法の基本原則である「罪刑法定主義」も、こういう主義があり、これを学ぶことが重要だ、という形ではなく、200年に及ぶ議論、本書の言葉でいう「なるほどパワー比べ」の結果という形で提示するなどしました。」
大村:「物語だけ読んでも楽しいし、後から解説だけ読んでもいい仕掛けだと思います。」
〈「なるほどパワー」について〉
大村:「「なるほどパワー」という言葉が出ましたので、その話に移りたいと思います。シリーズ全体は「なるほどパワーの法律講座」というタイトルがついていますが、ここは特徴的なつくりになっていると思います。これもお2人の中で最初から共通のコンセプトでしたか?」

西原:「「なるほどパワー」という言葉は、本になる段階で出てきましたね。12月に模擬裁判をすることを前提にすると、子どもに判決を書いてもらうには、最初に得た直感ではなく、双方の主張の理由を聞いた結果として、勝ち負けの旗を挙げてもらうのでなければ、ゼミの意味がなかったことになります。こちらの方が説得力がある主張だということを認めるために、どういう理由を評価するかということにフォーカスしていかないといけないと思いました。理由として通用するものとしないもの、メタレベルに上げていくことなどを子どもが見ていくようになりました。相手に納得してもらうため、どういう論じ方の転換をしていくかまで深めてもらうことを、「なるほどパワー」という言葉に込めていきました。」
〈1年分のテーマの配分に関して〉
大村:「本1冊は4章からなっていますが、ゼミとして1年分のテーマを揃えるにはどうされましたか?」
仲道:「最初は「刑罰とは何か」から始めると決めて走り出しました。実際にゼミをしてみたら子どもたちの連帯意識に触れて、次の回を「共犯」にし、次は模擬裁判をするという制約のため、「罪刑法定主義」。最後に、模擬裁判の素材としやすく、また法解釈の違いが結論に直結しやすい「正当防衛」が来る、と考えて4つになりました。」
西原:「憲法の条文の流れを思い浮かべながら、子どもの貧困の現状など、様々な環境に思いを巡らせてもらうにはどうしたらいいかと悩みました。議論がそれなりに分かれるテーマについては、学部ゼミのディベート論題の蓄積がありましたので、そこから、規制の必要性に対する悩み、侵害に対する悩み、子どもに身近なテーマかどうか等で選択しました。大学生とは違うので難しいところもありました。貧困、生存権について子どもの身近な世界に置き換える方法についてはかなり悩みましたし、ベストな切り口になっているのかどうか、そこは自信がありません。」
大村:「ご自身のやりたいテーマと議論させやすいテーマがうまくミックスされていると思いました。テーマの選択肢の幅みたいなものを見せてもらっていると感じました。」
〈サル山共和国という舞台設定の効果について〉
大村:「すでにお2人から話が出ていますが、サル山共和国という舞台設定は、確かに、生臭くなく面白いと思います。人間世界の事件ですと、子どもが自分たちの問題として考えるのは大変ですが、かといって、作られた仮想空間になじみがないと身が入りません。ゼミをされて、この設定をどうお感じですか?」
西原:「結果論として、かなり適切な選択だったと思います。子どもたちが人間としてサルより優位に立てるので、便利でした。」
仲道:「「サル山共和国の学校」という枠があったことが大きかったと思います。人間の先生が出てくると立場性があり、子どもの主体的な判断が妨げられる恐れがありますが、サルの先生なら子どもが判断者の目線に立てることがよかったと思います。」
大村:「サルの話というのは、現実の学校や生身の先生の制約を取り除くうえで非常に意味のあることと感じました。」
〈学校教育と法教育に関して〉
西原:「江戸川区子ども未来館は文化共育部の施設で、教育委員会とは別系統です。学校教育的制約から離れた独立性があります。」
大村:「子ども未来館でのゼミは学校の制約が少なく、内容も設定がサルの話だから、学校教育の制約が少ない。この本を副読本として学校で授業をするとしたら、どうなるでしょうか?」

仲道:「ディスカッション・リーダーとして大学生に入ってもらいましたが、人数不足のため音楽と1年生の先生にもディスカッション・リーダーをお願いしました。5・6年生になじみの少ない先生だったのでスムーズに進んだと思います。ただ、これを担任の先生にお願いすると、難しい部分が出てくるかもしれないと思います。」
大村:「子どもゼミの実践は、ある種の学校教育のイメージと緊張関係にあるということですね。学校でやるなら、教室と少し違う空間をセットしてもらって、仮に先生が入るとしても日常的でない役割を演じていただけるならば、学校にも「サル山」が作れるということと思います。」
西原:「子ども未来館では各学校から1~2名ずつ参加で、きょうだいは違うグループにしましたので、日常的友達関係は持ち込めませんでした。その場で新しく作る人間関係でやりました。それは、何でも言える安心空間でもありました。荒川区の実践では5・6年生をグループに均等に配分しましたが、1つの意見に引きずられやすい面が見られました。その場合はディスカッション・リーダーが引き戻しましたが、日常的力関係の影響は受けると感じました。」
大村:「「無知のベール」がかかった状態で判断してほしいということですね。「無知のベール」によって、ある部分を捨象して考えられる場を創り出したい。本の場合には、本の中に入ってもらえば、そういうことが経験できるということだと思います。」
〈この本の読み方について〉
大村:「この本の読み方のヒントなどを挙げていただけますか」
仲道:「1つの考え方しかないのではない、ということが基本線にあります。「なるほどパワー比べ」といって、2つの考え方が書かれていますが、そうではない考え方も読者には開かれていることが、この本を読むときにはお伝えしておかねばなりません。本に書かれていることは正しいという保証はなくて、子どもの考え方もこれまでの刑法学100年以上の歴史をひっくり返す可能性があると思いながら読んでほしいと思います。学校の先生方には、ここに書いてあることは大学の先生の説明だから、これ以外の説明はないとは思わないでいただきたいと思います。」
〈9月17日公開予定の「その2」に続きます。〉
うさぎのヤスヒコ、 憲法と出会う |
||
 |
著 者 判 型 頁 数 発行年月 定 価 発 行 |
西原博史 著 A5判 126頁 2014年4月 本体2,000円(税別) 太郎次郎社エディタス |
 |
||
| ページ見本 クリックすると大きくなります | ||
おさるのトーマス、刑法を知る |
||
 |
著 者 判 型 頁 数 発行年月 定 価 発 行 |
仲道祐樹 著 A5判 134頁 2014年4月 本体2,000円(税別) 太郎次郎社エディタス |
  |
||
| ページ見本 クリックすると大きくなります | ||
アーカイブ
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
カテゴリータイトル
- インタビュー (16)
- はじめに (1)
- 取材日記 (325)
- 報道から (5)
- 対談 「法学教育」をひらく (17)
- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)
- 年度まとめ (10)
- 往復書簡 (10)
- 河村先生から荒木先生へ (5)
- 荒木先生から河村先生へ (5)
- 教科書を見るシリーズ (21)
- 法教育素材シリーズ (7)
